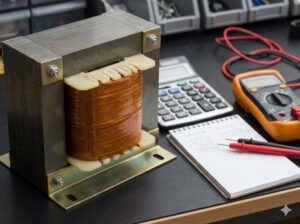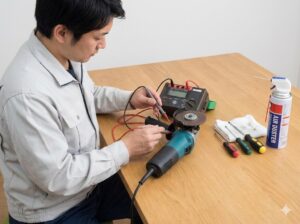2tトラックのタイヤ交換や日常整備において、2t トラック トルク レンチは、安全な運行を支えるために不可欠な工具です。
しかし、適切な締め付けトルクの管理は、乗用車とは比較にならないほどシビアであり、非常に重要です。
例えば、代表的な2tエルフの締め付けトルクや、車格が上がる4tトラックの締め付けトルクは、それぞれ厳密な規定値が異なります。
また、大型トラックのトルクレンチの使い方は、乗用車の整備とは異なる点も多く、「2tトラックのホイールナットのサイズは?」といった基本的な疑問や、「トラック トルクレンチ ソケットの選び方に迷う」という方も多いでしょう。
市場にはKTCのトラック 用 ト ルクレンチのようなプロ仕様の専用品もあれば、汎用性の高いト ルクレンチ トラック用モデルも存在します。
この記事では、「タイヤのトルクレンチは何Nですか?」という乗用車の整備でよく聞かれる疑問との違いから、「トルクレンチで103N・mに合わせるには?」といった具体的な設定方法、さらには名前が似ている「トルクスレンチの使い方は?」という点まで、2t トラック 締め付けトルクに関する専門的な情報を網羅的に解説します。
- 2tトラックや4tトラックのホイールナット規定トルクの目安と重要性
- トラック用トルクレンチの基本的な使い方、ソケットの適切な選び方
- KTCなど主要メーカーが提供するトラック用トルクレンチ製品の特徴
- トルクレンチの具体的な設定方法と、安全な運用・管理のための注意点
本記事の内容
2tトラックの整備とトルクレンチの基本
- ホイールナットのサイズは?
- ソケットの選び方
- エルフの締め付けトルク
- 4tトラックの締め付けトルク
- タイヤは何Nか?103N・m設定法
ホイールナットのサイズは?
2tトラックのホイールナットのサイズは、一つに定まっていません。 メーカー(いすゞ、日野、ふそう、UDトラックスなど)、製造年式、そして決定的に重要な要素としてホイールの規格(JIS方式かISO方式か)によって異なります。
一般的に、2tクラスのトラックでは、M20(ネジ径20mm、ピッチ1.5)やM22(ネジ径22mm、ピッチ1.5)といったサイズのナットが使用されることが多い傾向にあります。
ここで非常に重要なのは、ネジ径(M20など)と、工具(ソケット)選びに必要な「二面幅(対辺)」は異なる数値であるという点です。

ナットサイズとソケット対辺の一般的な例
- M22ナット(ISO方式で多い)の場合:
対辺 33mm のソケットが適合する情報があります。 - M20ナット(JIS方式で多い)の場合:
対辺 30mm や、他のサイズのソケットが必要になる場合があります。
これはあくまで一例に過ぎません。 JIS方式はナットの座面が球面、ISO方式は平面であるなど、形状も全く異なります。
最も確実な方法は、ご自身のトラックの「現車」のナットをノギスで正確に測定するか、車載工具や整備マニュアルで正しいソケットサイズ(対辺mm)を確認することです。
ソケットの選び方
トラック用の高トルクな作業において、ソケットの選定ミスは工具の破損や事故に直結します。 ソケットを選ぶ際は、以下の3つのポイントを必ず確認してください。
1. ナットの対辺サイズ(二面幅)
前述の通り、ご自身のトラックのナットに適合するサイズ(例:33mm)を選定します。 乗用車用の19mmや21mmのソケットは全く使用できません。
2. 差込角(ドライブ角)
トラックのような高トルク(数百N・m)での締め付け作業には、工具側の強度が求められます。 乗用車整備で主流の9.5sq(3/8インチ)や12.7sq(1/2インチ)では、規定トルクをかける前にラチェットのギアや差込角の根本が破損する危険性が非常に高いです。
トラック整備では、
- 19.0sq(3/4インチ)
- 25.4sq(1インチ)
といった、より太く高強度な差込角が必須となります。 必ず、使用するトルクレンチ本体の差込角と一致するソケットを選んでください。
3. ソケットの種類(インパクト用・ディープタイプ)
高トルクをかける作業では、通常のハンドツール用ソケット(銀色)よりも、強度と耐久性に優れる「インパクト用ソケット」(黒色)の使用が推奨されます。 また、トラックのホイールナットはボルトが長く突き出ていることが多いため、ソケット内部に深さがないとボルトの先端が当たり、ナットに正しく装着できません。 このため、「ディープソケット(深型)」が必要となるケースが一般的です。
エルフの締め付けトルク
いすゞ エルフ(2t)を含むトラックのホイールナット締め付けトルクは、法律(自動車点検基準)でも管理が義務付けられている、安全上非常に重要な項目です。
トラックの規定トルクは、前述の通りホイールの方式(JIS方式かISO方式か)、穴の数(6穴、8穴など)、ナットのサイズによって厳密に定められています。 同じ「エルフ」という名前でも、標準キャブかワイドキャブか、積載量、年式、タイヤの仕様(シングルかダブルか)によって、足回りの仕様が異なる可能性があります。

重大な注意:必ず正規のマニュアルでトルク値を確認してください
インターネット上の情報は、あくまで一般的な参考値でしかありません。 トルク不足は走行中のホイール脱落という重大事故に、オーバトルク(締め過ぎ)はホイールボルトの破損や伸びにつながり、同じく脱輪の原因となります。
必ず車載の取扱説明書、または車両ごとの整備マニュアルに記載されている正規のトルク値を確認し、その数値で締め付けを行ってください。
参考として、日本自動車工業会が過去にまとめた資料(平成19年時点)によると、「いすゞ」の「JIS/6穴」(2tクラスのフォワードなどで採用)の場合、以下の数値が示されています。
| メーカー | ホイール方式 | ねじサイズ(参考) | 規定トルク (N・m) |
|---|---|---|---|
| いすゞ | JIS/6穴 | 前 M24 / 後 M20, M30 | 440~490 N・m |
(参照:日本自動車工業会 大型車のホイールナット締付けトルク一覧)
このように、2tクラスであっても乗用車とは比較にならない、非常に高いトルク値(400N・m超)が設定されていることがわかります。
4tトラックの締め付けトルク
4tトラック(中型トラック)になると、車両総重量や積載量、タイヤサイズがさらに大きくなるため、2tトラックよりもさらに高いトルク管理が求められます。 4tクラスでは「JIS/8穴」方式が採用されていることが多くなります。

これも車種や仕様による正規マニュアルの確認が必須ですが、参考情報として「JIS/8穴」の規定トルクの例を以下に示します。 これらは日野「レンジャー」や三菱ふそう「ファイター」などの4tクラスの車種で採用されている規格です。
| メーカー | ホイール方式 | 規定トルク (N・m) |
|---|---|---|
| 日産ディーゼル | JIS/8穴 | 540~590 N・m |
| 日野 | JIS/8穴 | 540~590 N・m |
| 三菱ふそう | JIS/8穴 | 540~590 N・m |
(参照:日本自動車工業会 大型車のホイールナット締付けトルク一覧)
このように、4tクラスではおおむね550N・m前後のトルクが必要となることが分かります。 このため、4tトラックのトルクレンチを選定する際は、最低でも600N・m以上、余裕を見て800N・m程度まで測定できるモデルが推奨されます。 トルクレンチは、最大トルク値の80%以下で使うことが、精度維持と工具の寿命の観点から理想的とされています。
タイヤは何Nか?103N・m設定法
「タイヤのトルクレンチは何Nですか?」という疑問は、主に乗用車の整備において聞かれる質問です。
特に「103N・m(ニュートンメートル)」という数値は、トヨタの乗用車(コンパクトカーやセダン、ミニバンなど)で指定されていることが多い、非常に一般的なトルク値です。 この数値はあまりに一般的なため、KTCからも乗用車専用としてあらかじめ103N・mに設定された単能型トルクレンチ(WCMPA103など)が販売されているほどです。
しかし、前述の通り、2tトラックでは400N・m以上、4tトラックでは500N・m以上が必要であり、乗用車の103N・mとは比較にならない(約4~5倍の)大きな力が必要です。 最大測定値が200N・m程度の乗用車用トルクレンチをトラックに使うことは、トルクが全く足りないため論外であり、絶対にできません。

プレセット型レンチで103N・mに合わせる方法
もし、乗用車整備などで「103N・m」に設定する必要がある場合、プレセット型トルクレンチ(目盛が1N・m刻みのもの)では以下の手順で設定します。
- グリップエンドにあるロック機構を解除します(例:ロックリングを引き下げる)。
- グリップを回し、レンチ本体の「主目盛」の「100」のラインに、グリップ側の「副目盛」の「0」を合わせます。 (この時点で100N・mです)
- そこからさらにグリップを回し、副目盛の「3」のラインを、レンチ本体の中心線(主目盛の縦線)に合わせます。
- (主目盛100N・m)+(副目盛3N・m)= 合計103N・m となります。
- 最後にロックリングを戻してグリップを確実に固定し、作業中に設定がずれないようにします。
※副目盛の1目盛りが何N・mを示すか(1N・m刻みか、0.5N・m刻みかなど)は、レンチのモデルによって異なります。必ずお持ちのレンチの目盛を確認してください。
2tトラック用トルクレンチの使い方と選び方
- 大型トラック用の使い方解説
- トルクスレンチの使い方は?
- トラック用の主要製品
- KTC製の特徴
- 【まとめ】2t トラック用トルクレンチの選び方
大型トラック用の使い方解説
大型トラックのホイールナットを締める際、トルクレンチの使い方は安全に直結します。 ここでは、プレセット型やデジタル型の基本的な使い方と、安全に関わる最重要の注意点を解説します。
準備:清掃と潤滑
締め付け作業の前に、ディスクホイールの取付面、ハブの取付面、ホイールボルトのネジ部、ナットのネジ部と座面に付着した錆やゴミ、泥、古いグリスなどを徹底的に清掃します。 異物が挟まると、トルクレンチが「カチッ」と鳴っても、実際には適正な軸力(ボルトが部材を締め付ける力)が出ていない状態になり、緩みの原因となります。
また、潤滑剤の塗布は、ホイールの方式によって厳密にルールが異なります。
- JIS方式(球面座):
ボルトとナットのねじ部、およびナットの座面(球面)にエンジンオイルなどを薄く塗布します。 - ISO方式(平面座):
ボルトとナットのねじ部にエンジンオイルなどを薄く塗布します。
ナットの座面(ホイールと接触する平面部)には絶対に塗布しないでください。
このルールを間違えると、摩擦係数が変わり、適正な軸力が得られません。
基本的な締め付け手順
- トルク値の設定:
デジタルの場合は電源を入れ単位(N・m)を確認し数値を設定します。
プレセット型の場合はロックを解除し、主目盛と副目盛を合わせて規定トルク値を設定し、再度ロックします。 - ソケットの装着:
トラック用の正しいサイズ(対辺・差込角)のソケットを、レンチに奥までしっかりと差し込みます。 - 仮締め:
まずはトルクレンチを使わず、十字レンチやスピンナーハンドルで、必ず対角線順(星形を描くように)にナットを軽く締め付け、ホイールのセンターを出します。 - 本締め(トルクレンチ使用):
ソケットをナットに垂直に当て、ハンドルの中心(グリップ部分)を両手で握り、ゆっくりと一定の速度で力を加えます。
この時も必ず対角線順に締めます。 - 完了の合図:
- デジタルの場合:
設定値に近づくと断続音(ピッ、ピッ)が鳴り始め、設定値に達すると連続音(ピー)とLEDの点灯に変わります。 - プレセット型の場合:
設定値に達すると「カチッ」という音、または手に「コクッ」という軽いショック(トグルが作動した感触)が伝わります。
- デジタルの場合:
- 力を抜く:
合図があったら、即座に力を抜きます。
「カチッ、カチッ」と何度も鳴らすのは、オーバトルク(締め過ぎ)の原因となります。 - 増し締め:
ホイール取付後、50~100km走行後を目安に、必ず増し締め(再度トルクレンチで規定トルクがかかっているか確認)を行います。
初期なじみにより、締付け力が低下することがあるためです。

最重要禁止事項:絶対に「緩め作業」に使わない
トルクレンチは「締め付けトルクを管理する」ための精密な計測機器です。 固着したナットを緩めるような、大きな衝撃や高負荷をかける作業(破壊作業)には絶対に使用しないでください。
緩め作業にトルクレンチを使用すると、内部のトルクセンサーやトグル機構が一発で破損し、精度が完全に失われ、二度と正しいトルク測定ができなくなります。
ナットを緩める際は、必ず「スピンナーハンドル(ブレーカーバー)」や「倍力レンチ」など、高負荷に耐える専用の工具を使用してください。
トルクスレンチの使い方は?
ここで、名前が非常によく似ている「トルクスレンチ」について解説します。 これは「トルクレンチ」とは全く異なる目的の工具ですので、混同しないよう注意が必要です。
「トルクレンチ」と「トルクスレンチ」の決定的な違い
- トルクレンチ (Torque Wrench):
「トルク(回転力)」を測定・管理するための工具です。
設定した力でボルトやナットを締めるために使います。 - トルクスレンチ (Torx Wrench):
「トルクス」という星形のネジ(穴)の規格名です。
トルクスレンチは、この星形ネジを回すための工具(ドライバーやL字レンチ)の総称です。
トルクスネジは、プラスやマイナスのネジに比べて力の伝達効率が良く、ネジ頭を「舐めにくい(角が丸くなりにくい)」という特徴があるため、自動車の様々な箇所で採用されています。 トラック整備においても、内装パネル、エンジン補器類(オルタネーター固定部など)、ブレーキ周りのセンサー固定部などで見かけることがあります。

トルクスレンチの使い方は、L字型であれば六角レンチと同様に差し込んで回し、ドライバー型であれば通常のドライバーと同じです。
もし、「トルクスネジを、規定トルクで締め付けたい」という場合には、
「先端がトルクス形状になったソケット(トルクスソケット、またはビットソケット)」
を別途用意し、それを「トルクレンチ」に装着して、規定トルクで締め付け作業を行います。
トラック用の主要製品
2tトラックや4tトラックの整備に必要な高トルク(400N・m~800N・m程度)に対応するトルクレンチは、信頼性の高い専門メーカーから様々なモデルが販売されています。
プレセット型(機械式)
設定トルクに達すると「カチッ」という音や感触で知らせる、最も一般的なタイプです。 電源が不要で構造が比較的シンプルなため、現場での信頼性が高いのが特徴です。
- TONE (トネ):
T6L700N (700N・m) や T8L850N (850N・m) など、大型車向けのプレセット型レンチをラインナップしています。特に数値が直読式で設定ミスを減らせる「ダイレクトセットタイプ」が人気です。
- 東日製作所 (TOHNICHI):
トルクレンチの専門メーカーとして名高く、プロからの信頼が厚いです。QL/QLEシリーズ(プレセット型)や、大型車ホイールナット専用に設計されたTW型など、高品質で耐久性の高い製品を提供しています。
- モノタロウ (MonotaRO): 「トルクレンチ プレセット型 プロ用」として、高トルク対応モデルをコストパフォーマンス良く提供しています。±3%の高い精度を保証するモデルもあり、プロユースにも対応します。
デジタル型
設定トルク値を液晶画面で正確に設定でき、音と光で締め付け完了を知らせるため、作業者の熟練度を問わず均一な作業が可能です。
- ACDelco (エーシーデルコ):
ARM601シリーズなどで知られます。
ピークモード(締めた最大値を保持)やトレースモード(リアルタイムのトルクを表示)を備え、締め付け確認や緩みトルクの測定(※固着したボルトの緩め作業ではない)にも使用でき、多機能です。
- KTC (京都機械工具):
後述する「デジラチェ」シリーズで、高トルク対応モデルも展開しています。
トラック用を選ぶ際は、「トルク測定範囲」がご自身のトラックの規定トルク(例:450N・m)を十分にカバーしていること、そして「差込角」がトラック用ソケット(例:19.0sq)と適合していることを必ず確認してください。
KTC製の特徴
KTC(京都機械工具)は、日本を代表する高品質な工具メーカーとして、プロの整備士から絶大な信頼を得ています。 トラック用の高トルクに対応するトルクレンチも、機能と耐久性に優れた製品をラインナップしています。
プレセット型 (CMPB / GWシリーズ)
KTCのトラック用プレセット型レンチ(例:CMPB8006 [19.0sq/800N・m]、CMPB8008 [25.4sq/800N・m]、GW1000-06 [19.0sq/1000N・m])には、以下のような特徴があります。
- 視認性の高い目盛:
主目盛と副目盛が大きく読みやすく、トルク設定作業が快適に行えます。 - 確実なロック機構:
グリップ部にロック機構を搭載し、作業中に不用意に設定トルクが変動するのを防ぎます。 - 優れたグリップ:
GWシリーズなどでは、劣化に強く、オイルが付着した手でも滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 - 左右両方向測定(CMPBシリーズ):
KTCのCMPBシリーズは、ラチェットヘッドを反転させることで、逆ネジ(左回転)のトルク管理にも対応可能です。
(※プレセット型は右回転のみのモデルも多いため、これは大きな特徴です)
デジラチェ (GEKシリーズ)
KTCのデジタル式トルクレンチ「デジラチェ」にも、高トルク対応モデルが存在します。 音と光(LED)で設定トルクへの到達を段階的(例:90%で断続、100%で連続)に知らせるため、暗い場所や騒音が大きい場所でも締め付け完了を確実に認識できます。 また、「プレセットモード」の他に、現在のトルク値を表示する「計測モード」もあり、増し締め時の確認にも便利です。
電動トルクレンチ (JTAE481など)
さらにプロフェッショナルな現場向けに、KTCは電動式のトルクレンチも提供しています。 「JTAE481」のようなモデルは、最大800N・mといったハイパワーを電動で発生させます。 作業者の肉体的な負担を大幅に軽減しつつ、高精度なトルク管理を実現するため、多数のホイールを扱う現場での作業品質の均一化に大きく貢献します。
【まとめ】2t トラック用トルクレンチの選び方
最後に、2tトラックの整備と安全運行のために、最適なトルクレンチを選ぶための重要なポイントをまとめます。
- 最優先事項:自分のトラックの正規の締め付けトルク値を整備マニュアルで確認する
- ホイールの方式が「JIS方式」か「ISO方式」かを必ず確認する(トルク値や潤滑方法が異なる)
- レンチの「トルク測定範囲」が、規定トルク値を十分にカバーしているか(例:規定値450N・mなら、100~500N・mの範囲内のモデルを選ぶ)
- レンチの「差込角」が、使用するトラック用ソケット(19.0sqまたは25.4sq)と一致しているか
- プレセット型を選ぶ場合は、目盛の見やすさと、設定値を固定するロック機構の有無をチェックする
- デジタル型を選ぶ場合は、アラーム(音や光)の分かりやすさや、バッテリーの仕様を確認する
- KTC、TONE、東日製作所など、精度と耐久性で信頼できるメーカーの製品を選ぶ
- トルクレンチは「締め付け専用」の精密な計測機器であることを理解する
- 固着したナットを緩める作業には、スピンナーハンドルや倍力レンチを使い、トルクレンチは絶対に使用しない
- 保管時は、プレセット型のスプリング負荷を抜くため、必ずトルク値を測定範囲の最低値に戻しておく
- 使用後は汚れや水分を拭き取り、衝撃を与えないよう専用のハードケースで保管する
- トルクレンチは、精度を維持するために年に1回または一定の使用回数ごとに「校正」(精度チェックと調整)が必要
- 使用するソケットは、ナットの「対辺サイズ(mm)」を間違えず、強度のあるインパクト用ディープソケットを選ぶ
- 「トルクスレンチ」は星形ネジ用の工具であり、「トルクレンチ」とは全く別の工具であることを認識する
- 潤滑剤の塗布ルール(JISとISOの違い)を守ることが、正しいトルク管理につながる