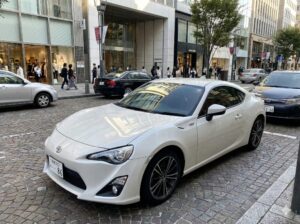cbn 砥石のデメリットを調べているものの、高価な工具だけに、導入して後悔しないか不安に思うかもしれません。
CBN砥石の硬さはどの程度で、一般的なダイヤとCBNの違いは何なのでしょうか。
この記事では、CBN砥石とは何かという基本特性から、CBN 砥石の際立った特徴、CBN砥石と一般砥石の違いを徹底比較します。さらに、最適なCBN 砥石の粒度の選び方、CBN 砥石の加工条件、厄介なCBN 砥石の目詰まり対策、そして性能維持に不可欠なCBN砥石のドレス方法やCBN砥石 ドレッサーの役割まで、専門的な情報を分かりやすく網羅的に解説します。

- CBN砥石が持つ「高コスト」以外の具体的なデメリット
- ダイヤモンド砥石や一般砥石との構造・用途の決定的違い
- 性能を100%引き出すための加工条件と粒度・集中度の選び方
- 砥石の寿命を延ばす目詰まり対策と正しいドレス方法
本記事の内容
cbn 砥石のデメリットと基本特性
- そもそもCBN砥石とは
- 複数の際立った特徴
- 砥粒の硬さはどの程度?
- 最大のメリットは?
- 一般砥石との違い
- ダイヤとの違いは何ですか?
そもそもCBN砥石とは
CBN砥石とは、CBN(Cubic Boron Nitride:立方晶窒化ホウ素)という、人工的に合成された化合物の砥粒(研磨剤の粒)を使用した研削工具を指します。
従来、硬い材料を削る工具としてはダイヤモンドが最強とされてきました。 しかし、ダイヤモンドには「熱に弱い」「鉄系の材料を加工すると化学反応を起こしやすい」という重大な弱点がありました。
このため、ダイヤモンドの弱点を克服する目的で開発されたのがCBNです。 CBNは、窒素(Nitride)とホウ素(Boron)から成る化合物であり、ダイヤモンドの結晶構造に似ていることから、ダイヤモンドに次ぐ非常に高い硬度を持っています。

自然界には存在しない物質であり、ダイヤモンドの合成法に似た、静的な高温高圧法を用いて人工的に製造されます。 この硬いCBN砥粒を、結合剤(ボンド)で固め、強固な円盤状の土台(台金)に焼き付けたものが、一般に「CBNホイール」または「CBN砥石」と呼ばれている工具です。
複数の際立った特徴
CBN砥石は、他の砥石にはない優れた特徴を複数持っています。 特に注目すべきは、「卓越した耐熱性」と「鉄系材料への化学的安定性」です。
第一に、CBNはダイヤモンドよりもはるかに熱に強い性質を持っています。 ダイヤモンドが約700℃で酸化し硬度が低下し始めるのに対し、CBNは約1300℃まで熱的な耐性を持つことが確認されています。研削加工中は砥粒の先端が非常に高温になるため、この耐熱性は極めて重要です。
第二に、鉄との反応性が極めて低い点です。 ダイヤモンドは炭素(C)で構成されているため、高温になると鉄(Fe)と化学反応を起こし、ダイヤモンドが黒鉛化して摩耗が激しくなります。 一方、CBNは窒素とホウ素からできており炭素を含まないため、高温下でも鉄系材料(鋼や鋳鉄など)と反応しにくい特性を持つのです。

さらに、熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が非常に高いことも大きな特徴です。 加工中に発生した熱を素早く砥石内部や加工物へ逃がすことができるため、加工対象物の表面温度上昇を抑え、熱による「焼け」や「ひずみ」、組織の変質を防ぎ、品質の高い加工結果につながります。
CBNの主な特徴
- 高い耐熱性:
約1300℃まで安定しており、高温になりがちな研削加工に適しています。 - 鉄との反応性が低い:
鉄系材料(炭素鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼など)の研削に最適です。 - 高い熱伝導率:
加工熱を効率よく逃がし、加工物の焼けや変形を防ぎます。 - 高い硬度:
ダイヤモンドに次ぐ硬さを持ち、優れた切れ味を発揮します。
砥粒の硬さはどの程度?
CBN砥石の砥粒の硬さは、「ダイヤモンドに次ぐ硬さ」と表現されます。
物質の硬さを示す指標の一つに「ヌープ硬度」がありますが、CBNはダイヤモンドに非常に近い値を示します。 これは、一般的な研削砥石に使われる砥粒(アルミナや炭化ケイ素)と比較すると約2倍、多くの切削工具に使われる超硬合金と比較しても約3倍近い圧倒的な硬度です。
この硬さがあるからこそ、CBN砥石は他の工具では加工が困難な材料を効率よく削ることが可能になります。 具体的には、HRC45~65程度の硬度を持つ高硬度材料の研削に最適です。
- 焼入れ鋼(SKD、SKSなど)
- 高速度鋼(ハイス:SKH)
- ベアリング鋼(SUJ)
- 耐熱鋼

ただし、前述の通り、高温下(約700℃以上)においてはCBNの方がダイヤモンドよりも硬度を維持できるという逆転現象が起こります。 鉄系材料の加工では、加工点が高温になりやすいため、耐熱性と硬度を両立するCBNの優位性が際立つのです。
最大のメリットは?
CBN砥石を使用する最大のメリットは、「高効率な精密加工の実現」と「工具寿命の長さ」にあります。
前述の通り、CBNは高い硬度と耐熱性を持ち、鉄系材料との反応性も低いです。 このため、焼き入れ鋼や工具鋼などの硬い材料を研削する際に、砥石の摩耗(すり減り)を大幅に抑えることができます。
摩耗が少ないということは、砥石の形状が崩れにくいことを意味します。 これにより、高い加工精度を長期間にわたって維持できる点が大きな強みです。
また、工具交換の頻度が劇的に少なくなるため、連続加工や自動化ラインにおいて生産性を大きく向上させることが可能です。 結果として、工具の単価は高くても、交換の手間や再調整の時間を削減できるため、トータルのランニングコストを下げられるケースが多くあります。
木工旋盤の刃物研ぎの世界でも、このメリットが注目されています。 従来の砥石では研ぐことが物理的に困難だったM42ハイス鋼や粉末ハイス(内部に硬いカーバイトを多く含む)も、CBN砥石なら短時間で鋭利な刃先に仕上げられるため、急速に普及が進んでいます。
一般砥石との違い
CBN砥石と、安価な一般砥石(ホワイトアランダム[WA]や炭化ケイ素[GC]など)の最も大きな違いは、「砥粒の硬度」と「砥石の構造」にあります。
CBN砥石は、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ「超砥粒」を使用しています。 一方、一般砥石の砥粒はCBNに比べると硬度が低くなります。
構造については、一般砥石が砥粒と結合剤で全体が構成されているのに対し、CBN砥石は「台金」と呼ばれる金属の基盤(ホイール)の外周部分にだけ、CBN砥粒と結合剤で構成された「砥粒層」が薄く設けられているのが一般的です。
この構造の違いは、メンテナンス性に大きな影響を与えます。 一般砥石は使用するたびにすり減って直径が小さくなるため、研削盤の設定を頻繁に調整する必要があります。 一方、CBN砥石は砥粒層が摩耗するだけなので、砥石の直径がほとんど変わらず、設定変更の手間を削減できるメリットがあります。
| 比較項目 | CBN砥石 (超砥粒ホイール) | 一般砥石 (WA, GCなど) |
|---|---|---|
| 砥粒 | CBN (立方晶窒化ホウ素) | アルミナ、炭化ケイ素など |
| 硬度 | 非常に高い (ダイヤに次ぐ) | CBNより低い |
| 構造 | 台金に薄い砥粒層がある | 全体が砥粒と結合剤で構成 |
| 主な用途 | 高硬度の鉄系材料 (焼入れ鋼など) | 生材、非鉄金属、非金属など |
| 寿命 | 非常に長い | 短い (摩耗しやすい) |
| 価格 | 高価 | 安価 |
| メンテナンス | ドレスが難しい (専用ドレッサー要) | ドレスが比較的容易 |
| 使用中の直径 | ほぼ変化しない | 使用と共に小さくなる |
ダイヤとの違いは何ですか?
ダイヤモンド(ダイヤ)とCBNは、どちらも「超砥粒」と呼ばれ非常に硬い物質ですが、決定的な違いは「耐熱性」と「鉄との反応性」にあります。
結論から言えば、「鉄系材料にはCBN、非鉄系・非金属材料にはダイヤモンド」というのが、工具を選定する際の絶対的な大原則です。
ダイヤモンドは地球上で最も硬い物質ですが、約700℃を超えると性能が低下し始め、高温では鉄と化学反応を起こしやすいという致命的な弱点があります。 これは、ダイヤモンドを構成する炭素(C)が、高温下で鉄(Fe)の中に溶け込んでしまう(固溶)現象が発生し、砥粒が急速に摩耗するためです。 このため、鉄、炭素鋼、ステンレス鋼などの「鉄系材料」の研削には絶対に適していません。
一方、CBNはダイヤモンドに次ぐ硬さを持ちながら、約1300℃までの高い耐熱性を誇ります。 さらに、炭素を含まないため高温でも鉄と反応しません。 この特性により、ダイヤモンドが苦手とする焼き入れ鋼やハイス鋼など、硬い鉄系材料の加工に最適なのです。

被削材による使い分けの目安
- CBNに適した材料 (鉄系):
炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼(ハイス)、ステンレス鋼、焼結金属、ニッケル合金、鋳鉄 など。 - ダイヤモンドに適した材料 (非鉄・非金属):
超硬合金、サーメット、セラミックス、ガラス、石英、シリコン、アルミニウム合金、銅合金、ゴム、樹脂 など。
cbn砥石のデメリットと実用上の注意点
- 欠点は何ですか?
- 適切な加工条件は?
- 粒度の選び方
- 目詰まり対策
- ドレス方法
- ドレッサーとは
- CBN砥石のデメリットの総括
欠点は何ですか?
CBN工具やCBN砥石は非常に高性能ですが、導入や運用にあたってはいくつかの欠点(デメリット)を正確に理解しておく必要があります。
最大のデメリットは、「高コスト」である点です。 CBN砥粒自体が人工的に高温高圧で合成される高価な材料であるため、一般砥石と比較すると製品の単価が数倍から数十倍になることも珍しくありません。
また、「鉄系材料であっても極端な高温下では化学摩耗する」場合があります。 CBNは鉄と反応しにくいとはいえ、研削熱が極端に高くなるとCBN砥石が「刃が立たなく」なる(切れ味が著しく低下する)現象が報告されています。これはクーラントの選定ミスなどで起こり得ます。
他にも、硬い一方で衝撃には弱い(曲げ強さや靭性が低い)ため、刃先に強い力がかかる荒加工でチッピング(微小な欠け)を起こしやすい点も注意が必要です。

CBN砥石の主なデメリット
- 高コスト:
一般砥石に比べて導入費用が非常に高いです。 - 特定の加工に不向き:
- 極端な高温になる鉄系材料の研削(化学摩耗の可能性)。
- 衝撃に弱く、チッピングしやすいため荒加工には向きません。
- #400より細かい粒度や、#40より粗い粒度は一般的でなく、選択肢が限られます。
- メンテナンスの難しさ:
成形やドレス(後述)が難しく、専用の道具やノウハウが必要です。
適切な加工条件は?
CBN砥石の性能を最大限に引き出すには、適切な加工条件、特に「クーラント(研削液)」の選定が非常に重要です。
CBN砥石を使用する場合、原則として油性クーラントの使用が強く推奨されます。
その理由は、CBN(立方晶窒化ホウ素)が高温のアルカリ水溶液と化学反応を起こす性質があるためです。 一般的な水溶性クーラントの多くは防錆のためにアルカリ性(pH8~10程度)に調整されており、研削熱によって高温になったCBN砥粒と反応すると、砥粒が化学的に分解・摩耗してしまう可能性があります。
ある情報によれば、CBNは300℃のアルカリ溶液中では分解し、沸騰水中でもわずかに分解する可能性があるとされています。 このため、化学反応を避け、高い潤滑性で加工点を保護できる油性クーラントが適しているのです。乾式(クーラントなし)での研削は、熱を持ちやすく寿命が低下するため、鏡面加工などには向きません。
粒度の選び方
CBN砥石の選定では、「粒度」と「集中度」という2つの重要な指標を考慮する必要があります。
1. 粒度(#)
「粒度」とは、砥粒の大きさを示す尺度で、「#(番手)」という記号で表されます。 粒度の選び方は、「加工の目的(荒削りか、仕上げか)」によって決まります。
- 数字が小さい(#80, #100など):
砥粒が粗い。一度に削る量が多く、荒加工に適しています。 - 数字が大きい(#170, #200など):
砥粒が細かい。削る量は少なく、仕上げ加工(面粗さを良くする)に適しています。
被削材(加工する材料)が軟らかい場合や、砥石と材料が接する面積が広い場合は、目詰まりを防ぐために粗めの粒度(数字が小さいもの)を選ぶのが一般的です。
2. 集中度(Concentration)
「集中度」とは、砥粒層に含まれるCBN砥粒の含有割合(密度)を示す指標です。 砥粒層1cm³あたりにCBNが4.4カラット(0.88g)含まれる状態を「集中度100」と定義しています。
- 集中度が高い (例: 125, 150):
砥粒の数が多いため、砥石の寿命は長くなります。
ただし、価格は高くなり、切れ味が重くなる(研削抵抗が上がる)傾向があります。 - 集中度が低い (例: 75):
砥粒の数が少ないため、切れ味は鋭くなります(研削抵抗が下がる)。
しかし、砥粒一つあたりの負荷が大きくなるため、寿命は短くなる傾向があります。
加工の効率、寿命、コストのバランスを考え、一般的には集中度75~125の範囲で選定されます。
目詰まり対策
CBN砥石も使用を続けると、目詰まり、目つぶれ、目こぼれといった「切れ刃の劣化」が発生し、切れ味が著しく低下します。
- 目詰まり (Loading):
砥粒と砥粒の隙間に削りカス(切り屑)が詰まった状態。
特にアルミニウムや銅のような軟らかい金属(非鉄金属)を加工した際に発生しやすいです。 - 目つぶれ (Glazing):
砥粒の先端が摩耗して平らになり、切れ刃がなくなった状態。
硬すぎる材料を加工したり、硬すぎる結合剤(ボンド)の砥石を選んだりすると発生します。 - 目こぼれ (Shedding):
砥粒が結合剤(ボンド)から脱落してしまった状態。
結合剤が柔らかすぎる場合や、過度な負荷がかかった場合に発生します。
これらの現象が発生すると、切れ味が悪くなるだけでなく、摩擦熱が過剰に発生し、加工物に「焼け」や「割れ」を引き起こす原因にもなります。
最も重要かつ基本的な対策は、定期的な「ドレッシング(ドレス)」を行い、砥石の表面をリフレッシュすることです。 日常的には、クーラントを適切に管理し(清浄な液を十分にかける)、加工条件を最適化することが目詰まりの予防につながります。
ドレス方法
CBN砥石の性能を維持するためには、「ツルーイング」と「ドレッシング(ドレス)」という2つのメンテナンス作業が不可欠です。
- ツルーイング:
砥石の形状を整える作業(形直し)。
使用によって生じた歪みや偏心を修正し、正確な円形に戻します。 - ドレッシング:
砥石の表面の目詰まりや目つぶれを取り除き、新しい砥粒を露出させて切れ味を回復させる作業(目直し)。
CBN砥石は非常に硬いため、これらの作業は一般砥石よりも難しく、専用の道具(ドレッサー)が必要です。 ドレス方法は、砥石の結合剤(ボンド)の種類によって異なります。

1. レジンボンド・メタルボンドホイールの場合
普通砥石法(WA/GC法)がよく用いられます。 これは、WA(ホワイトアルミナ)やGC(緑色炭化ケイ素)といった一般砥石のスティック(棒状の砥石)を、回転するCBNホイールに押し当てることで、目詰まりの解消と目立て(砥粒の突き出し)を同時に行う方法です。 また、レジンボンドの場合は、軟鋼材(生材)をドレッサー代わりに使用し、実際に研削することで目立てを行う方法も有効です。
2. ビトリファイドボンドホイールの場合
ビトリファイドボンド(ガラス質)は硬く脆い特性があるため、切れ味の回復(ドレッシング)と形状の維持(ツルーイング)を高いレベルで両立する必要があります。 ロータリドレッサ(回転するダイヤモンド工具)など、高精度なドレッサーを用いた方法が推奨されます。
3. 電着ホイールの場合
電着ホイールは、台金にCBN砥粒が一層だけメッキで固着されている構造です。 このため、ツルーイングやドレッシングは行えません。 切れ味が落ちたら寿命となり、交換または再電着(張り替え)が必要です。
ドレッサーとは
CBN砥石のドレッサーとは、前述のツルーイングやドレッシングを行うための専用工具です。
CBN砥石自体が非常に硬いため、ドレッサーにはダイヤモンドが使われることが多くあります。
主なドレッサーの種類
- 単石ドレッサ (シングルポイントドレッサ)
鉛筆のような形状のシャンク(持ち手)の先端に、ダイヤモンドの原石を1個セットしたドレッサーです。
機械に固定し、回転する砥石の中心に対して5~15度程度傾けて当て、左右にスライドさせて砥石表面を削ります。
傾けるのは、ダイヤモンドの先端が平らに摩耗するのを防ぎ、常に鋭利な角が当たるようにするためです。
高精度なツルーイングに適していますが、定期的にドレッサー自体を回転させる管理が必要です。 - 多石ドレッサ (マルチポイントドレッサ)
複数のダイヤモンド砥粒をブロック状や板状に配置したドレッサーです。
単石ドレッサよりも広い面積を一度にドレスでき、安定した作業が可能です。量産加工での使用に適しています。 - ロータリドレッサ
表面にダイヤモンドが埋め込まれた円筒状の工具で、ドレッサー自体も回転させながら砥石を成形・ドレスします。
高精度で複雑な形状の砥石を短時間で成形でき、自動化ラインなどで多用されます。 - 普通砥石スティック(WA/GC)
前項の「ドレス方法」で触れた通り、主にレジンボンドやメタルボンドの「ドレッシング(目直し・目詰まり解消)」に特化して使用される簡易的なドレッサーです。
CBN砥石は高価な工具ですが、その性能は適切なメンテナンスによってのみ維持されます。 高価だからこそ、ドレッシングの手間を惜しまず、その特性を理解して使いこなすことが、結果的にコストパフォーマンスを高める鍵となります。
CBN砥石のデメリットの総括
この記事では、CBN砥石のデメリットと、その背景にある特性やメリット、適切な運用方法について詳細に解説しました。 最後に、本記事の要点をリストでまとめます。
- CBN砥石とは立方晶窒化ホウ素という人工化合物の砥粒を使った工具である
- ダイヤモンドの弱点(熱と鉄との反応)を克服するために開発された
- CBNはダイヤモンドに次ぐ硬さを持ち HRC45以上の高硬度材に適する
- CBNは熱に強く約1300℃まで耐性がある
- ダイヤモンドは約700℃で性能が低下し始める
- CBNは炭素を含まず高温でも鉄系材料と反応しにくい
- ダイヤモンドは高温で鉄と反応するため鉄系材料には不向きである
- 使い分けは 鉄系材料にはCBN 非鉄系材料にはダイヤモンド が基本
- CBNのメリットは高硬度材を効率よく加工でき長寿命であること
- 摩耗が少なく砥石径が変わらないため自動化にも向いている
- cbn 砥石の最大のデメリットは一般砥石に比べ高コストであること
- その他のデメリットは衝撃に弱いことや成形が難しいこと
- 粒度の選択肢が一般砥石に比べて少ない点も短所と言える
- 加工条件として油性クーラントの使用が推奨される
- 水溶性クーラントは高温のアルカリと反応しCBNが分解する恐れがあるため
- 粒度(粗さ)と共に集中度(密度)も選定の重要指標である
- 砥石の劣化には目詰まり・目つぶれ・目こぼれの3種類がある
- これらの劣化を解消し切れ味を戻す作業がドレッシングである
- 形状を整える作業はツルーイングと呼ばれる
- ドレス方法はボンドの種類で異なり レジンにはWAスティック ビトリファイドにはロータリドレッサが使われる
- 電着タイプの砥石は一層構造のためドレッシングができない
- ドレッサーには単石・多石・ロータリなどがありダイヤモンドが使われる