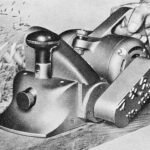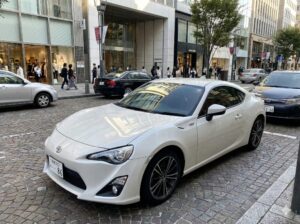第二種電気工事士の技能試験で、多くの受験者が練習を重ねる必須作業「のの字曲げ」。
この作業について、「先端が細いラジオペンチを使った方が、綺麗で簡単な輪が作れるのではないか?」と感じている方も少なくないでしょう。
確かに、細かい輪作りをラジオペンチで行うイメージは湧きやすく、一見すると効率的に思えるかもしれません。
しかし、実際の試験では、どののの字曲げ工具を選択するかが、作業の質とスピード、ひいては合否そのものを大きく左右します。
不適切な工具選びや使い方は、心線に深い傷をつけてしまう「のの字曲げ傷」や、輪がネジの座金から大きくはみ出す「のの字曲げのはみ出し」といった、一発で不合格となる「のの字曲げの欠陥」に直結する危険性をはらんでいます。
電気工事士のの字曲げではペンチが基本とされていますが、その具体的な理由や、正しいのの字曲げのコツを深く理解できているでしょうか。

この記事では、のの字曲げにラジオペンチは使えるのかという核心的な疑問に答えつつ、試験で推奨されるホーザンののの字曲げの方法、さらには作業を劇的に楽にする合格のの字曲げツールまで、あらゆる角度から深く掘り下げて徹底解説します。
この記事で分かること
- ラジオペンチでのの字曲げの可否と具体的なリスク
- ペンチや専用ツールを使ったプロレベルの正しい輪作り方法
- 技能試験で一発失格となる7つの主要な欠陥パターンと対策
- 作業時間を5分短縮するための実践的なのの字曲げのコツ
本記事の内容
第二種電気工事士「のの字曲げ」にラジオペンチは有効か
- 工具の基本とそれぞれの役割
- 輪作りをラジオペンチで行うメリットとは
- 電気工事士はペンチが基本の理由
- 推奨品ホーザン製のポイント
- 「合格のの字曲げツール」という選択肢
工具の基本とそれぞれの役割
第二種電気工事士の技能試験における「のの字曲げ」では、主に3種類の工具が候補に挙がります。
それは、「ペンチ」「VVFストリッパー」、そして今回のテーマである「ラジオペンチ」です。
それぞれの工具には明確な長所と短所があり、その役割を深く理解して適材適所で使い分けることが、正確無比でスピーディーな作業を実現するための鍵となります。
まず、最も基本であり、かつ最も重要な工具はペンチです。
電線の切断、屈曲、固着した部品の掴みといった、電気工事の基本作業を力強くこなすための万能選手です。
特にのの字曲げにおいては、心線をしっかりと固定し、安定した力で滑らかに曲げられるため、多くの受験者や現場で活躍するプロの電気工事士に標準工具として絶対的な信頼を置かれています。
次に、VVFストリッパーは、現代の技能試験において時間短縮の切り札となる工具です。
「ケーブルの切断・外装被覆剥き・絶縁被覆剥き・のの字曲げ・寸法測定」といった複数の機能をたった1本でこなせる極めて優秀な多機能工具です。
工具を持ち替えるタイムロスを完全に排除できるため、試験全体の作業時間を大幅に短縮する効果が期待でき、今や必須のアイテムと言っても過言ではありません。

最後にラジオペンチは、その名の通り、元々はラジオの組み立てのような精密作業で使われていた工具で、先端が細長いのが最大の特徴です。
狭い場所での作業や、小さな電子部品を正確に掴むのに適しています。
のの字曲げにおいては、その細さを活かして小さな輪を作りやすいと感じるかもしれませんが、掴む力が弱かったり、先端で心線を傷つけやすかったりする、試験では致命的となるデメリットも内包しています。
| 工具の種類 | 長所(メリット) | 短所(デメリット) |
|---|---|---|
| ペンチ | 把握力が非常に強い 安定した力で正確な加工が可能 太い電線の切断や曲げも容易 | 先端が太いため、微細な調整は不向き 重量があるため、 長時間の作業で疲れやすい場合がある |
| VVFストリッパー | 圧倒的な時間短縮効果 1本で複数作業をこなし、 工具の持ち替えが不要 のの字曲げ専用の機能が 付いているモデルもある | ペンチに比べて把握力や切断能力は劣る 多機能ゆえに、 一つの機能の専門性はペンチに及ばない |
| ラジオペンチ | 先端が細く、視認性が良い 細かい作業や微調整がしやすい 狭い場所での作業に適している | 把握力が弱く、 心線を傷つけるリスクが非常に高い 2.0mm心線など、太い電線の加工には不向き |
受験案内の規定について
ちなみに、第二種電気工事士の受験案内では、使用工具について「電動工具でないものすべて」と記載されています。
この規定上は、ラジオペンチを使用すること自体がルール違反になるわけではありません。
ただし、試験で推奨される工具には、長年の経験則に基づいた「作業を最も効率的かつ安全に進めるための理由」が凝縮されていることを理解しておくことが、合格への最短ルートです。
輪作りをラジオペンチで行うメリットとは
「結局、輪作り(のの字曲げ)をラジオペンチで行うのはダメなの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、ラジオペンチを使うことには、限定的な状況下でのメリットが確かに存在します。しかし、それは熟練者がリスクを理解した上で選択するレベルの話です。
最大のメリットとして挙げられるのは、やはり先端が細いことによる視認性の高さと、細かい作業のしやすさです。
ペンチに比べて先端が細長いため、自分が心線のどこを掴んで、どのように曲げているのかを視覚的に正確に把握できます。
特に、ランプレセプタクルや露出形コンセントの小さなネジ頭に合わせた、直径の小さい輪を作りたい場合には、ラジオペンチの細さが有利に働くことがあります。
また、ペンチよりも繊細な力加減の調整がしやすいため、指先でつまむような感覚で、自分のイメージ通りの完璧な円形に近づけやすいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、これらのメリットは、技能試験という環境下では非常に大きなデメリットと表裏一体であることを、強く認識する必要があります。

メリットを帳消しにする致命的なリスク
ラジオペンチは細かい作業が得意な反面、根本的に把握力が弱いため、2.0mmのような太い心線を曲げる際に力が逃げやすく、何度も握り直すことになり、かえって時間がかかってしまうケースが頻発します。
さらに、最も警戒すべきは、先端が鋭利なため、少しでも力を入れすぎたり、手が滑ったりすると心線に深い傷をつけてしまうリスクが極めて高い点です。
技能試験において心線の傷は、その深さに関わらず重大な欠陥とみなされるため、このデメリットは、ラジオペンチが持つわずかなメリットを完全に打ち消してしまうほど大きいと言えるでしょう。
電気工事士はペンチが基本の理由
全ての教材や講習会で「電気工事士ののの字曲げはペンチが基本」と口を酸っぱくして言われるのには、複数の明確な理由が存在します。
それは、作業の確実性、効率性、そして再現性が、制限時間内に完璧な施工を求められる技能試験では何よりも重視されるからです。
理由1:圧倒的な作業の安定性
ペンチは、十分な力で心線をがっちりと掴み、ブレることなく安定して曲げられる点において、他の工具の追随を許しません。
技能試験で主に使用されるVVFケーブルの心線(1.6mmや2.0mm)は、想像以上に反発力が強く、硬さがあります。
ラジオペンチのような華奢な工具では、力が逃げてしまったり、最悪の場合、工具が弾かれてしまったりする可能性がありますが、ペンチであれば一度で確実に、そして安全に曲げることが可能です。
理由2:工具自体が「定規」になる効率性
推奨されるJIS規格のペンチは、技能試験の施工条件に最適化されているものが多く存在します。
例えば、ペンチの刃の付け根部分の幅が、絶縁被覆を剥く長さの目安(約11~12mm)になるように設計されている製品があります。
このように、工具自体がスケール(定規)の代わりになることで、いちいち寸法を測る手間を省き、思考停止で作業を進めることができ、大幅なスピードアップに貢献します。

試験本番では「5分の差」が合否を分ける
技能試験は40分という、非常に短い制限時間との戦いです。
慣れない工具を使ったり、腰袋の中の工具の種類が多すぎたりすると、「あれ、あの工具はどこだっけ?」と探す時間が発生し、これが焦りの引き金になります。
例えば、工具を探したり持ち替えたりする時間でトータル5分の差が出たとします。残り15分で完成するはずが残り10分になるのと、残り5分のはずが時間切れになるのとでは、全く意味が違います。
ペンチとVVFストリッパーという最小限かつ最強の基本工具に習熟し、体に覚え込ませることが、精神的な安定にもつながり、結果的に致命的なミスを防ぐ最大の防御策となるのです。
推奨品ホーザン製のポイント
第二種電気工事士技能試験の推奨工具として、長年にわたり多くの受験者に選ばれ続けているのがホーザン(HOZAN)の製品です。
特に圧着ペンチ「P-43-175」やVVFストリッパー「P-958」は、その使いやすさと信頼性から「三種の神器」とも称される定番工具です。
ここでは、ホーザンのペンチを使った、より実践的なのの字曲げの手順とポイントを詳細に解説します。
手順1:絶縁被覆を剥く
まず、電工ナイフやVVFストリッパーを使い、心線の絶縁被覆を剥きます。
このとき、長さは約20mm程度、少し長めに剥いておくのが失敗を防ぐ重要なコツです。
後工程で余分な長さを正確にカットするため、この段階で短すぎてしまうと修正が効かなくなります。
手順2:根本を90度に曲げる
絶縁被覆の根元から2〜3mm(完成した輪の「首」となる部分)離した箇所を、ペンチの平らな部分(刃の裏側)で地面と水平になるように、かつ、しっかりと掴みます。
そして、ペンチは動かさず固定したまま、心線を指で正確に90度折り曲げます。捻じれた輪にならないよう、真上に曲げる意識が重要です。
手順3:余分な部分をカットする
90度に曲げた部分の根元に、ペンチの刃をぴったりと密着させ、余分な心線をカットします。
このとき、ペンチの刃の厚み分だけ、約1mm程度の先端がちょこんと残る形になります。
この、わずかに残った先端部分が、綺麗な円を作るための「芯」となり、仕上がりを格段に向上させます。
手順4:輪を作り、形を整える
最後に、心線の先端をペンチの角(先端の平らな部分と刃の境目あたり)で軽くつまむように掴み、手首を返すようにして一気に円形に曲げます。
「ためらわず、一回で滑らかに曲げ切る」ことが、傷のない綺麗な「の」の字を作る最大の秘訣です。
輪の大きさは、ペンチで掴む位置を先端側にすれば小さく、根元側にすれば大きくなります。器具のネジの大きさに合う位置を、練習で体に覚え込ませましょう。
ホーザンのペンチは、多くのプロが最初の1本に選ぶだけあって、本当に信頼できます。
手に吸い付くようなグリップと絶妙な重量バランスが、長時間の練習でも疲れを軽減してくれます。
工具選びは合格への投資です。迷ったら、まずは多くの合格者を支えてきた定番品から試してみるのが、最も確実な選択です!
「合格のの字曲げツール」という選択肢
「何度練習しても、どうしてもペンチでのの字曲げが上手くできない…」
「もっと簡単で、誰でも確実に綺麗な輪を作れる魔法のような方法はないの?」
そんな切実な悩みを持つ受験生のために、近年注目を集めているのが「合格のの字曲げツール」という、その名の通り、のの字曲げを極限まで簡単にするために開発された専用工具です。
このツールが持つ最大の特徴は、心線を巻き付けるための軸(マンドレル)が、理想的な大きさの円形になっている点です。
ペンチのように「掴んで曲げる」という、感覚と熟練を要する作業ではなく、「円形の軸に沿って、ただ巻き付けるだけ」という単純な作業に変わるため、スキルレベルに関わらず、誰が使っても均一で美しい円を、しかも驚くほどスピーディーに作ることができます。
もう一つの非常に大きなメリットは、心線に傷が付くリスクがほぼゼロになることです。
ペンチの場合、どうしても「掴む」という行為が伴うため、力の入れすぎや掴む場所のミスで心線に傷がつくリスクが常に付きまといます。
しかし、このツールは滑らかな軸に心線を沿わせるだけなので、その心配が根本的にありません。
「傷による一発不合格」という、最も避けたいリスクを物理的に排除できるのは、精神衛生上も非常に大きなアドバンテージです。
こんな人におすすめ!
このツールは、特に以下のような方に心強い味方となります。
- 手先の器用さに自信がなく、ペンチでの作業に苦手意識がある方
- 仕事や学業が忙しく、十分な練習時間を確保できない方
- 試験本番でのプレッシャーに弱く、少しでもミスする要因を減らしたい方
製品によっては、プラスドライバーが一体化していたり、曲がってしまった心線を真っ直ぐに矯正できるスロットが付いていたりと、便利な機能が搭載されているものもあります。
まさに「転ばぬ先の杖」として、腰袋に一つ忍ばせておけば、本番で予期せぬトラブルに見舞われた際にも冷静に対処できるでしょう。
ラジオペンチでの「のの字曲げ」欠陥対策と上達のコツ
- 芯線に傷を付けない注意点
- キレイに作るコツを掴む練習
- 一発失格となる欠陥の具体例
- はみ出しを防ぐ調整方法
- 技能試験での「のの字曲げ」ラジオペンチ使用まとめ
芯線に傷を付けない注意点
技能試験において、心線(導体)の傷は、たとえわずかであっても重大な欠陥と見なされ、即不合格につながります。
なぜなら、心線の傷は断線の原因になるだけでなく、その部分の断面積を減少させ、電気抵抗を増加させることで、発熱や火災といった深刻な事故を引き起こす可能性があるからです。
特にラジオペンチを使用する場合、先端が鋭利で掴む面も小さいため、傷がつきやすく、細心の注意が求められます。

傷を付けないための鉄則
傷を防ぐための最も重要かつ絶対的なルールは、「工具のギザギザの部分(滑り止め)で心線を直接掴まない」ことです。
ペンチやラジオペンチの先端には、物をしっかりと掴むための溝(セレーション)が刻まれていますが、この部分で柔らかい銅線を掴むと、ひとたまりもなく傷だらけになってしまいます。
のの字曲げを行う際は、必ずペンチの刃の付け根に近い、表面が平滑な面(サイドカッターの裏側など)を利用して心線を掴む癖をつけましょう。
また、工具を滑らせながら曲げるような動作も、摩擦熱やエッジで傷がつく原因になるため厳禁です。「置くように掴み、固定して曲げる」という動作を徹底してください。
全ての工程で「傷」への意識を!
心線の傷は、のの字曲げの工程だけでなく、ケーブルの被覆を剥く最初の段階でも発生しやすい非常に厄介な欠陥です。
電工ナイフの刃を深く入れすぎたり、VVFストリッパーの刃のサイズ設定を間違えたりすると、絶縁被覆を貫通して心線にまで刃が届いてしまいます。
被覆剥きから輪作り、そして器具への取り付けまで、全ての作業工程を通して常に「大切な心線を絶対に傷つけない」という強い意識を持つことが、合格の最低条件です。
キレイに作るコツを掴む練習
のの字曲げは、自転車の乗り方と同じで、一度コツを掴んでしまえば無意識にできるようになります。
そのためには、正しい手順と感覚を、頭ではなく手が覚えるまで、ひたすら反復練習することが唯一にして最強の上達法です。
ただやみくもに繰り返すのではなく、以下のコツを意識することで、上達のスピードは飛躍的に向上します。
キレイな輪を作るための最大のコツは、「一筆書きのイメージで、迷わず、滑らかに一度で曲げる」ことです。
途中で動きを止めたり、何度も形を修正しようとしたりすると、輪がカクカクと歪になったり、修正の過程で不要な傷が付いたりする原因になります。
ペンチの先端で心線を掴んだら、迷わずに手首をクルッと返す。
このリズミカルで淀みのない動作を、体に染み込ませることが目標です。
また、輪の「首」部分の寸法精度も、仕上がりの美しさを左右します。
絶縁被覆の根元から2〜3mm程度の「首」を正確に作ることで、ネジで締め付けた際に輪が安定し、被覆を噛み込む欠陥も防げます。
練習の際は、この「首」の長さを常に意識し、毎回同じ長さにできるよう集中してください。
練習を始めたばかりの頃は、いきなり100点満点の完璧な輪を目指さなくて大丈夫です。
最初は「①必ず右巻き(時計回り)にする」「②輪の大きさをネジ頭に合わせる」「③傷をつけない」という3つの基本ポイントから確実にクリアしていきましょう。
端材のケーブルをたくさん用意して、無心で曲げ続ける時間を作るのが一番の近道です。
ある瞬間、本当に「あ、これか!」と感覚が掴める時が必ず来ますから、諦めずに続けてください!

一発失格となる欠陥の具体例
技能試験では、たった一つの「欠陥」が、それまでの努力を全て無にしてしまいます。
のの字曲げに関連する欠陥は、そのほとんどが「知っていれば防げる」ものです。
ここでは、一発失格となる代表的な欠陥のパターンを、その理由とともに詳しく見ていきましょう。これらのミスを犯すと、他の部分がどれだけ完璧でも不合格となります。
- 【欠陥1】左巻き(逆巻き)
ネジは時計回りに締まるため、のの字も必ず同じ方向(時計回り/右巻き)に作る必要があります。
逆向きに作ると、ネジを締める力で輪が開く方向に力がかかり、確実な結線ができず、接触不良や発熱の原因となります。 - 【欠陥2】輪が短い・重なっている
輪を曲げすぎて、心線の先端が根元部分と重なってしまっている状態です。
ネジで締めた際に先端が浮き上がり、接触面積が不安定になるため欠陥とされます。 - 【欠陥3】輪が大きすぎる(はみ出し)
ネジ頭の座金(ワッシャー)部分から、心線がはみ出してしまっている状態です。
詳細は次の見出しで解説しますが、隣の端子との短絡(ショート)につながる極めて危険な欠陥です。 - 【欠陥4】心線の露出が長すぎる(首長)
輪の「首」の部分が規定以上に長く、充電部が不必要に露出している状態です。
これも短絡や感電のリスクを高めるため、欠陥となります。 - 【欠陥5】絶縁被覆の噛み込み
逆に「首」が短すぎたり、輪が小さすぎたりして、ネジを締めた際に絶縁被覆を巻き込んでしまっている状態です。
銅線とネジが直接触れず、導通不良(電気が流れない)の原因となります。

「機能」を満たしているかが判断基準
欠陥の基準を知ることは非常に重要ですが、芸術品を作るわけではないので、過度に神経質になる必要はありません。
例えば、輪の形が完全な真円でなくても、ネジで締め付けた際に座金全体にしっかりと接触し、電気的に安全な接続という「機能」を満たしていれば、それは欠陥にはなりません。
どこからが欠陥で、どこまでが許容範囲なのか。
その線引きを正しく理解し、絶対に外してはいけない重要なポイントを確実に押さえることが、効率的な練習と合格につながります。
はみ出しを防ぐ調整方法
数あるのの字曲げの欠陥の中でも、特に初心者が陥りやすく、かつ重大なミスと判断されるのが「輪が大きすぎてネジの座金からはみ出してしまう」という欠陥です。
これは見た目が悪いというだけでなく、隣の端子との距離が近くなり、短絡(ショート)を引き起こす直接的な原因となるため、試験官は非常に厳しくチェックします。

この「はみ出し」を確実に防ぐための調整方法は、主に2つのアプローチがあります。
1. ペンチで掴む位置を体に覚えさせる
輪の直径は、ペンチのどの部分で心線を掴んで曲げるかによって、ほぼ決まります。
ペンチの先端に近い細い部分で曲げれば小さな輪になり、根元に近い太い部分で曲げれば大きな輪になります。
まずは、自分が愛用するペンチのどの位置で曲げれば、ランプレセプタクルやコンセントのネジにジャストフィットする大きさの輪になるのか、その「黄金ポジション」を練習によって体に徹底的に覚え込ませることが最も重要です。一度覚えてしまえば、本番でも無意識に再現できます。
2. カットする心線の長さを最適化する
前述ののの字曲げの手順で、90度に曲げた後に余分な心線をカットする工程がありました。
このとき、カットせずに残す心線の長さを調整することでも、輪の大きさをコントロールできます。
残す長さを少し短くすれば小さな輪に、長くすれば大きな輪になります。ホーザンの推奨手順のように、刃の厚み分だけ残すのが一つの基準ですが、自分の癖に合わせて微調整するのも有効です。
ただし、この方法は調整がシビアで上級者向けなので、まずは基本である「ペンチで掴む位置」で調整できるよう練習するのが王道です。
「現物合わせ」の最終チェックを習慣に
のの字曲げが完成したら、それで終わりではありません。
必ず、実際に取り付ける予定の器具(ランプレセプタクルなど)のネジに当ててみて、はみ出しがないかを最終確認する癖をつけましょう。
もしこの段階で少しでも大きいと感じた場合は、時間を惜しまず、勇気を持って作り直すべきです。
本番で焦らないためにも、「製作→現物合わせで確認→必要なら修正」という一連の品質管理プロセスを、普段の練習からルーティンとして取り入れておくことを強くお勧めします。
技能試験での「のの字曲げ」ラジオペンチ使用まとめ
- のの字曲げは第二種電気工事士技能試験の合否を分ける重要作業
- 受験案内の規定上、ラジオペンチの使用自体は禁止されていない
- ラジオペンチは先端が細く、視認性が良く細かい作業がしやすいという限定的なメリットがある
- しかし把握力が弱く、特に2.0mm心線の加工には不向き
- 最大のデメリットは心線を傷つけるリスクが極めて高いこと
- 技能試験では確実性と効率性の観点からペンチの使用が絶対的な基本となる
- 推奨品のペンチは刃幅が寸法ガイドになるなど作業効率を上げる工夫がされている
- VVFストリッパーは1本で複数機能をこなし、試験全体の時間短縮に大きく貢献する
- ホーザン製のP-43-175やP-958は、多くの合格者を支えてきた定番工具である
- どうしてもペンチ作業が苦手な場合、合格のの字曲げツールも有効な選択肢
- 専用ツールは傷のリスクを物理的に排除し、誰でも均一な輪を作れる
- 心線の傷は、たとえわずかでも重大欠陥と見なされ一発不合格となる
- 傷防止の鉄則は、工具のギザギザ部分で心線を直接掴まないこと
- 練習では一筆書きのイメージで、一度に滑らかに曲げ切る動作を体に覚えさせる
- 欠陥には左巻き、輪の重なり、はみ出し、首長、被覆噛み込みなどがある
- 特に輪がネジの座金からはみ出す欠陥は、短絡の危険があるため厳しく見られる
- 輪の大きさは、ペンチで心線を掴む位置を調整してコントロールするのが基本
- 完成後は必ず器具のネジに合わせる「現物確認」を習慣づけることが重要
- 一つの欠陥が全ての努力を無にするのが技能試験の厳しさである
- 基本工具に習熟し、正しい手順を反復練習することが合格への最短ルート