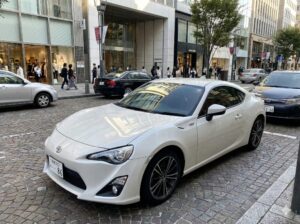BAL(大橋産業)のトルクレンチを購入したものの、正しいトルク値の合わせ方や具体的な使い方で悩んでいませんか。
「トルクレンチのトルク値の合わせ方は?」
「トルクレンチで103N・mに合わせるにはどうすればいいの?」
といった具体的な数値設定で戸惑う声は少なくありません。また、BALトルクレンチNo.2059の使い方やBALトルクレンチ2060の使い方、そしてBalトルクレンチ2059と2060の違いが分からず、どちらを選ぶべきか迷っている方もいるでしょう。
この記事では、そんな疑問を解決するために、基本的なbal トルク レンチ 合わせ 方から、モデルごとの特徴まで詳しく解説します。大橋産業トルクレンチの評価や、クロスレンチとトルクレンチの評判を比較し、BALトルクレンチNo.2059の評価も客観的にまとめました。さらに、長く安全に使うために知っておきたいBalトルクレンチの校正や大橋産業トルクレンチの校正の必要性、そして意外と知らないトルクレンチでやってはいけないことまで、網羅的に情報をお届けします。
- BALトルクレンチの基本的なトルク設定方法がわかる
- モデルごとの特徴や使い方の違いが理解できる
- 購入前に知っておきたい評価や評判を確認できる
- トルクレンチを安全に長く使うための注意点が学べる
本記事の内容
基本的なbal トルク レンチ 合わせ 方と手順
- トルク値の合わせ方は?
- 具体例:103N mに合わせるには?
- BAL No.2059の基本的な使い方
- BAL No.2060の具体的な使い方
- 注意!トルクレンチでやってはいけないこと
トルク値の合わせ方は?
プレセット型トルクレンチのトルク値設定は、「主目盛」と「副目盛」という2種類の目盛りを組み合わせて行います。これは、大橋産業(BAL)のトルクレンチをはじめ、多くの製品で共通する基本的な仕組みです。
設定手順は、まずトルクレンチのグリップエンドにあるロックを解除することから始まります。ロックを解除したら、グリップ部分を回転させて、締め付けたいトルク値に近い数値を「主目盛」で合わせます。
次に、グリップをさらに回転させ、「副目盛」で細かい数値を調整します。主目盛の数値に副目盛の数値を足したものが、最終的な設定トルク値となります。例えば、主目盛で100N・mに合わせ、副目盛で3N・mを加えれば、合計103N・mに設定できるというわけです。

トルク設定の基本ステップ
- グリップエンドのロックを解除する。
- グリップを回し、目標値に近い数値を主目盛で合わせる。
- さらにグリップを回し、残りの細かい数値を副目盛で合わせる。
- 目標の数値になったら、グリップエンドをロックして設定完了。
この方法を理解すれば、誰でも簡単に正確なトルク管理ができるようになります。最初は少し戸惑うかもしれませんが、一度覚えてしまえば難しい作業ではありません。
具体例:103N mに合わせるには?
それでは、より具体的に「103N・m」に設定する方法を解説します。ここでは、主目盛が10N・m刻み、副目盛が1N・m刻みのトルクレンチを例に取ります。
まず結論として、主目盛を「100N・m」の位置に設定し、副目盛で「3N・m」を追加します。

具体的な手順は以下の通りです。
手順1:主目盛を合わせる
グリップのロックを解除した後、グリップ全体を時計回りに回転させていきます。本体に刻まれている主目盛の「100」という数字の刻印線と、副目盛の「0」のラインがぴったり重なる位置まで回してください。この時点で、トルクレンチは100N・mに設定されています。
手順2:副目盛で微調整する
次に、現在の100N・mの状態から、さらにグリップを時計回りに回していきます。副目盛には0から始まる数字が刻まれており、グリップを回していくと「1」「2」「3」…と数字が主目盛の中央線に合っていきます。今回は103N・mに設定したいので、副目盛の「3」のラインが主目盛の中央線に一致するまで回します。
計算式: 主目盛(100N・m) + 副目盛(3N・m) = 目標トルク(103N・m)
これで、トルクレンチの設定は103N・mになりました。最後に、設定値が作業中にずれないように、グリップエンドのロックを確実に締めてから使用してください。この手順は、120N・mなど他の数値に合わせる場合も同様に応用できます。
BAL No.2059の基本的な使い方
大橋産業(BAL)のトルクレンチ「No.2059」は、DIYユーザーから人気の高いモデルです。ここでは、その基本的な使い方をステップごとに解説します。

仕様の確認
まず、No.2059の基本的なスペックを把握しておきましょう。トルク測定範囲は30~180N・mとなっており、多くの乗用車のホイールナット締め付けトルクに対応しています。
使用手順
- ロックの解除:
グリップエンドにあるロックつまみを反時計方向に止まるまで回し、ロックを解除します。
使用後の保管時はこの状態で保管するため、最初は回るかどうかを確認する作業になります。 - トルク設定:
前述の方法で、本体グリップを回して指定トルクに設定します。
「主目盛」と「副目盛」の合計で数値を合わせます。 - ロックの固定:
トルク設定後、ロックつまみを時計方向に止まるまで回して、グリップが動かないように固定します。 - 締め付け作業:
ソケットを取り付け、ボルトやナットを締め付けていきます。
設定したトルクに達すると、ヘッド部分から「カチッ」という音と共に、手に軽い衝撃が伝わります。これが設定トルクに到達した合図ですので、それ以上力を加えるのはやめましょう。 - 保管:
使用後は、必ずロックつまみを反時計方向に回してロックを解除し、グリップを一番緩い状態(最低トルク値)まで戻してからケースに保管します。
使用後にトルクを最低値に戻すのは、内部のスプリングのへたりを防ぎ、精度を長く保つための重要な作業です。これを怠ると、トルクレンチの寿命を縮める原因になりますので、忘れないようにしましょう。
BAL No.2060の具体的な使い方
BALのトルクレンチ「No.2060」は、No.2059よりも広いトルク範囲を持つモデルで、こちらも非常に人気があります。基本的な使い方はNo.2059と共通していますが、目盛りの仕様が少し異なるため、その点に注意が必要です。

仕様と目盛りの特徴
No.2060のトルク設定範囲は28~210N・mです。副目盛は、1周で28目盛(28N・m)となっており、半周で14目盛(14N・m)となります。1目盛あたりは1N・mです。
この特徴を理解することが、No.2060を使いこなすポイントになります。
設定例:108N・mに合わせる場合
例えば、締め付けトルクが108N・mの車両の場合、以下のように設定します。
- まず、主目盛の「98N・m」のラインが見えるまでグリップを回します。
- 次に、副目盛の「0」を主目盛のセンターラインに合わせます。この時点で設定値は98N・mです。
- そこから、108N・mにするために、さらに10N・m分グリップを回します。つまり、副目盛の「10」のラインをセンターラインに合わせます。
計算式: 主目盛(98N・m) + 副目盛(10N・m) = 目標トルク(108N・m)
このように、主目盛の数字がキリの良い数字でない場合でも、副目盛との組み合わせで正確なトルク値を設定することが可能です。一見複雑に感じるかもしれませんが、仕組みを理解すれば直感的に操作できるようになります。
注意!トルクレンチでやってはいけないこと
トルクレンチは精密な測定工具です。その性能を維持し、安全に使用するためには、いくつかの禁止事項があります。誤った使い方をすると、工具の破損や精度の低下、さらには車両の重大なトラブルに繋がる可能性もあるため、必ず守ってください。
トルクレンチ使用時の主な禁止事項
- 逆回転での使用:
ほとんどのトルクレンチは締め付け専用(右回転のみ)です。
ボルトやナットを緩める作業には絶対に使用しないでください。内部の測定機構が破損する原因となります。 - 設定範囲外での使用:
トルクレンチにはそれぞれ測定可能なトルク範囲が定められています。
その範囲を超えたり、下回ったりするトルクでの使用は避けてください。 - 「カチッ」となった後の増し締め:
プレセット型トルクレンチは、設定トルクに達すると音や感触で知らせてくれます。
合図があった後にさらに力を加える「ダブルチェック」は、オーバートルクの原因となるため厳禁です。 - トルクをかけたままの保管:
使用後は、必ずトルク設定を最低値に戻してから保管してください。
スプリングに負荷がかかったままだと、精度が狂う原因になります。 - 衝撃を与える行為:
トルクレンチをハンマー代わりに使ったり、高い場所から落としたりしないでください。
精密な内部機構にダメージを与え、正確な測定ができなくなります。
これらの注意点を守ることが、トルクレンチの精度を長期間維持し、安全な作業を行うための鍵となります。

モデル別のbal トルクレンチの合わせ方と評判
- Bal No.2059と2060の違いを比較
- 大橋産業製トルクレンチの評価
- クロス&トルクレンチの評判をチェック
- 定期的な校正は必要か?
- 大橋産業トルクレンチの校正について
- まとめ:bal トルクレンチの合わせ方の要点
Bal No.2059と2060の違いを比較
大橋産業(BAL)から販売されている人気のトルクレンチ、No.2059とNo.2060。どちらもコストパフォーマンスに優れた製品ですが、いくつかの違いがあります。どちらを選ぶべきか迷っている方は、以下の比較表を参考にしてください。
| 項目 | トルクレンチ No.2059 | トルクレンチ No.2060 |
|---|---|---|
| トルク設定範囲 | 30~180N・m | 28~210N・m |
| 角ドライブ | 12.7mm | 12.7mm |
| 精度 | ±3% | ±3% |
| 全長 | 450mm | 非公開(No.2059とほぼ同等と推測) |
| 質量 | 1.32kg | 非公開(No.2059とほぼ同等と推測) |
| 付属品 | ディープソケット(17/19/21mm)、 エクステンションバー(150mm) | ディープソケット(19/21mm)、 エクステンションバー(125mm) |
主な違いと選び方のポイント
最大の違いはトルク設定範囲です。No.2060の方がより低いトルクから、より高いトルクまで対応しているため、対応車種の幅が広いです。特に、締め付けトルクが高めに設定されている車種(SUVなど)や、逆に低めのトルク管理が必要な箇所にも使いたい場合に有利です。
一方で、付属品のソケットにも違いがあります。No.2059には17mmのソケットが付属しますが、No.2060には付属しません。ご自身の車で必要なソケットサイズを確認して選ぶと良いでしょう。
選び方のまとめ
- 幅広い車種に対応したい、より高いトルクが必要な可能性がある → No.2060
- 一般的な乗用車での使用がメイン、17mmソケットが必要 → No.2059
ご自身の用途と必要なスペックを照らし合わせて、最適なモデルを選ぶことが重要です。
大橋産業製トルクレンチの評価
大橋産業(BAL)のトルクレンチは、DIYで車のメンテナンスを行うユーザーから高い評価を得ています。その理由を、実際のユーザーレビューなどから分析してみましょう。
高評価のポイント
- コストパフォーマンス:
最も多く見られる評価が「価格の安さ」です。
専門メーカーの製品に比べて手頃な価格でありながら、必要な機能や付属品(ソケット、ケース)が揃っている点が支持されています。 - 十分な精度:
プロ用の工具ではありませんが、精度は±3%とされており、DIY用途としては十分な性能を持っています。
「カチッ」という音と感触で設定トルクを知らせる機能も、締めすぎを防ぐ安心感に繋がっているようです。 - 使いやすさ:
シンプルな構造で、一度使い方を覚えれば直感的に操作できる点も好評です。
初めてトルクレンチを使う人でも扱いやすいという意見が多く見られます。
気になる点・注意点
一方で、価格相応の点として、いくつかの注意点を指摘する声もあります。
- ロック機構の緩み:
一部のユーザーからは「使用中にトルク設定のロックが緩んで、設定値が変わってしまうことがある」という報告があります。
作業中は、こまめに設定値がずれていないか確認することが推奨されます。 - 切り替えレバーの操作感:
ラチェットの締め/緩めを切り替えるレバーが、少し固かったり、節度が分かりにくかったりする場合があるようです。
使用前には、確実にレバーがセットされているか確認する習慣をつけると安全です。
総じて、いくつかの注意点はあるものの、価格を考えれば非常に満足度の高い製品であると言えます。DIYでのタイヤ交換や基本的なメンテナンスが目的であれば、十分な性能と品質を持っていると評価されています。
クロス&トルクレンチの評判をチェック
タイヤ交換の工具として、古くから使われている「クロスレンチ」と、正確なトルク管理ができる「トルクレンチ」。それぞれの評判や役割について考えてみましょう。
クロスレンチは、十字の形状により早回しがしやすく、仮締めやナットを緩める際には非常に効率的な工具です。しかし、最終的な締め付けをクロスレンチだけで行う、いわゆる「手ルクレンチ」には、いくつかの懸念点があります。
手ルクレンチの課題
ユーザーレビューの中には、「長年、感覚で締めていてトラブルはなかった」という声もありますが、同時に「トルクレンチで測定してみたら、締め付けトルクに結構なバラツキがあった」という報告も少なくありません。
手ルクレンチ(感覚による締め付け)の問題点
- 締め付けトルクのバラツキ:
均等な力で締め付けているつもりでも、ホイールナットごとに強弱が生まれてしまう可能性があります。 - オーバートルクのリスク:
必要以上に強く締め付けすぎると、ボルトが伸びたり、最悪の場合は破損したりする危険性があります。 - トルク不足のリスク:
締め付けが弱いと、走行中にナットが緩み、脱輪などの重大な事故に繋がる恐れがあります。
これらの理由から、クロスレンチはあくまで仮締めや緩める作業用と割り切り、最終的な本締めはトルクレンチで行うのが最も安全で確実な方法と言えます。クロスレンチの利便性と、トルクレンチの正確性を組み合わせることが、理想的なタイヤ交換作業に繋がります。
定期的な校正は必要か?
「トルクレンチに校正は必要なのか?」これは多くのDIYユーザーが抱く疑問の一つです。結論から言うと、トルクレンチの精度を保証するためには、定期的な校正が推奨されます。
トルクレンチは、内部のスプリングの力を利用してトルクを測定する精密工具です。使用頻度や経年変化、保管状況などによってスプリングがへたると、表示される数値と実際のトルク値にズレが生じてきます。
校正の必要性
プロの整備工場など、安全性が厳しく求められる現場では、年に1回など定期的な校正が義務付けられていることがほとんどです。これは、不正確なトルクレンチを使い続けるリスクを避けるためです。
しかし、年に数回のタイヤ交換にしか使用しない一般的なDIYユースの場合、毎回厳密な校正を行うのはコスト的にも現実的ではないかもしれません。
DIYユーザーの場合の考え方
DIYで使用する場合、厳密な定期校正は必須とまでは言えないかもしれませんが、少なくとも「トルクレンチは精度が狂う可能性がある測定工具である」という認識を持つことが重要です。落下などの強い衝撃を与えてしまった場合や、長年使用している場合は、一度トルクチェッカーで点検したり、校正サービスを検討したりすることをおすすめします。
正しい保管方法(使用後に最低トルクに戻す、湿気を避けるなど)を守ることで、精度の狂いを最小限に抑えることも可能です。
大橋産業トルクレンチの校正について
それでは、大橋産業(BAL)のトルクレンチは校正が可能なのでしょうか。
ユーザーレビューの中には、「台湾製で、校正もできるみたい」といった情報が見られます。これは、BALのトルクレンチが使い捨てではなく、精度を維持しながら長く使える可能性があることを示唆しています。
一般的に、トルクレンチの校正は、メーカー自身が行う場合と、トルクレンチ専門の校正業者が行う場合があります。大橋産業が公式に校正サービスを提供しているかどうかの詳細は、公式サイトや取扱説明書で確認する必要があります。

もしメーカーの公式サービスがない場合でも、専門の校正業者に依頼することで対応してもらえる可能性は十分にあります。その際は、校正にかかる費用と、新品を購入する費用を比較検討することになるでしょう。
BALのトルクレンチは比較的手頃な価格であるため、校正費用によっては新品に買い替える方が経済的な場合もあります。しかし、愛着のある工具を長く使い続けたいという場合は、校正サービスを探してみる価値はあると言えます。
具体的な校正方法や費用については、大橋産業のカスタマーサービスや、トルクレンチの校正を専門に行う業者に問い合わせてみるのが確実です。
まとめ:bal トルクレンチの合わせ方の要点
この記事では、BALトルクレンチの合わせ方を中心に、モデルごとの違いや使い方、注意点について解説しました。最後に、記事全体の要点をリスト形式でまとめます。
- BALトルクレンチのトルク設定は主目盛と副目盛を組み合わせて行う
- トルク設定はロックを解除し、グリップを回して調整する
- 103N・mに合わせるには主目盛100N・m+副目盛3N・mのように設定する
- No.2059のトルク範囲は30~180N・mで基本的な使い方を覚えることが重要
- No.2060は28~210N・mとより広い範囲に対応している
- No.2059とNo.2060の主な違いはトルク範囲と付属品のソケット
- トルクレンチを緩める方向(逆回転)で使用してはいけない
- 設定トルクに達した後の増し締め(ダブルチェック)はオーバートルクの原因になる
- 使用後は必ず最低トルク値に戻してスプリングの負荷を抜いてから保管する
- 大橋産業のトルクレンチはコストパフォーマンスの高さで評価されている
- 一方でロック機構の緩みなど価格相応の注意点も存在する
- クロスレンチでの本締めはトルクのバラツキが生じる可能性がある
- 安全のため最終的な締め付けにはトルクレンチの使用が推奨される
- トルクレンチは精密工具であり、長期間の精度維持には校正が望ましい
- この記事が正しいbal トルク レンチ 合わせ 方の理解に繋がれば幸いです