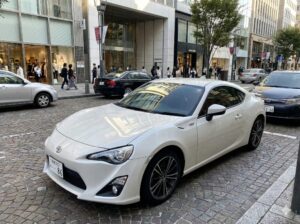FlexiSpotの電動昇降デスクを導入し、その快適さに満足しているものの、何か一つ物足りなさを感じていませんか。
デスクの裏側で配線を整理したい時、部屋の模様替えをしたい時、あるいは掃除の時。
「この重いデスクが、もっと手軽に動かせたら…」
と感じる瞬間は少なくないはずです。
その最後のピースを埋めるのが、キャスターの取り付けです。
しかし、多くの方が「キャスターを買ったはいいが、工具がなくて取り付けられない」という壁に直面します。

この記事では、flexispotのキャスター取り付けに不可欠なスパナの選び方から、具体的な取り付け方、そして導入後に後悔しないための重要な注意点まで、あらゆる情報を徹底的に解説します。
flexispotのおすすめキャスター情報はもちろんのこと、純正品であるフレキシスポットW2とW3の違いは何ですか?といった詳細な比較や、FlexiSpotのネジのサイズ、キャスターの耐荷重、設置による高さの変化、そして気になる床への傷を防ぐための具体的な対策など、購入前に抱くであろう全ての疑問に答えます。
このガイドを読めば、スパナ選びで迷うことなく、あなたのFlexiSpotデスクをさらに完璧な作業環境へと進化させることができるでしょう。
- 自分のデスクに合うスパナの正確なサイズと選び方が明確になる
- 価格と性能を比較し、最適な純正・社外品キャスターを見つけられる
- 安全で確実な取り付け手順と、後付けする際の具体的な方法がわかる
- キャスター導入後の高さの変化や床の傷など、デメリットへの対策がわかる
本記事の内容
flexispotキャスターの取り付けに適したスパナ
- スパナの具体的なサイズ
- ネジのサイズは?
- 取り付け方を解説
- W2とW3の違いは何ですか?
- 純正と社外品、どちらがおすすめ?
- キャスターの耐荷重は?
スパナの具体的なサイズ
FlexiSpotの新型純正キャスター(W2、W3モデル)や多くの社外品キャスターには、残念ながら取り付け用の工具が付属していません。そのため、キャスターをデスクに取り付けるには、ご自身で適切な工具を事前に準備しておく必要があります。
キャスターの根本にある六角形のナットを確実に締め付けるために最適な工具は、「二面幅寸法14mm」で「厚さが3mm以下」の薄型スパナ、通称「板スパナ」です。
なぜ「薄型」でなければならないのか?
このサイズが絶対条件である理由は、キャスターの構造にあります。ナット部分は、ホイールを支えるハウジング(金具)とデスク脚の取り付け面の間にあり、その隙間が非常に狭く設計されています。一般的な家庭用工具セットに入っているような厚みのあるモンキーレンチやメガネレンチでは、物理的にこの隙間に入らず、ナットを回すことができません。必ず「薄型」であることを確認しましょう。
この特殊なスパナは、ホームセンターの工具売り場や、Amazonなどのオンラインストアで簡単に見つけることができます。価格も100円から数百円程度と非常に手頃です。特に「ユーエイキャスター製 14平スパナ」は、厚みが約2mmと極薄で作業がしやすく、多くのユーザーから支持されています。キャスター本体が届いてから慌てないよう、あらかじめ購入しておくことを強くおすすめします。
ネジのサイズは?
FlexiSpot昇降デスクの脚の裏側には、標準でアジャスター(床面のガタつきを調整するための円盤状の足)が取り付けられています。このアジャスターを回して外し、そのネジ穴にキャスターを装着することになります。
この重要なネジ穴の規格は、現在販売されているほとんどのFlexiSpotデスクで「M8」サイズに統一されています。
「M8」とは、ネジの直径が約8mmであることを示す国際的な規格です。この情報さえ知っていれば、FlexiSpotの純正キャスターに限定されず、市場に流通している膨大な数の社外品キャスターの中から、ご自身の予算や好みに合った製品を自由に選ぶことが可能になります。これは、カスタマイズ性を高める上で非常に重要なポイントです。
社外品キャスター選びの際の確認事項
社外品キャスターの製品仕様を確認する際は、必ず「ネジ規格:M8」や「ねじの種類:M8」といった記載があることを確認してください。M6(直径6mm)やM10(直径10mm)といった異なる規格の製品は、物理的に取り付けることができません。また、ネジの長さ(ネジ山の部分)については、一般的に15mm前後の製品であれば問題なく適合するとされています。
このM8規格は、オフィスチェアや家具、一部のモニターアームなどにも広く採用されている非常にポピュラーなサイズです。そのため、コストを抑えたい、床に優しいウレタン素材のホイールが良い、デザインにこだわりたい、といった様々なニーズに応える製品が見つかりやすいという大きなメリットがあります。

取り付け方を解説
FlexiSpotデスクへのキャスター取り付けは、正しい手順と少しの注意点を守れば、誰でも安全に行うことができます。DIYが苦手な方でも安心して取り組めるよう、ステップごとに詳しく解説します。
ステップ1:デスク上の完全な整理
作業を始める前に、デスクの上にあるPC、モニター、スピーカー、書類など、すべての物を完全に撤去します。これは、作業中の落下による破損を防ぐだけでなく、デスクの総重量を少しでも軽くし、後の工程を安全に進めるための最も重要な準備です。
ステップ2:デスクを安全に横に倒す
次に、デスクをゆっくりと横に倒し、脚部が上を向くようにします。フローリングや天板に傷がつかないよう、床には必ず古い毛布やラグ、購入時の段ボールなどを敷いて養生してください。
重量物注意!二人以上での作業を徹底
FlexiSpotのデスクフレームと天板を合わせた総重量は、モデルによっては50kgを優に超えます。成人男性であっても一人で持ち上げて安全に倒すのは非常に困難であり、転倒による家財の破損や、腰を痛めるなどの怪我に繋がる重大なリスクがあります。この工程は、必ず家族や友人に手伝ってもらい、二人以上で慎重に行ってください。
ステップ3:標準アジャスターの取り外し
デスクの脚の裏に4つ付いている、標準の黒いアジャスターを手で反時計回りに回して取り外します。ここは特に工具は必要なく、簡単に外せるはずです。
ステップ4:キャスターの確実な取り付け
アジャスターが外れたネジ穴に、購入したキャスターを時計回りにねじ込んでいきます。まずは手で回せるところまで締め、最後に幅14mmの薄型スパナを使って、しっかりと増し締めします。この時、力を入れすぎてネジ山を破損させないよう注意してください。「キュッ」と締まる感覚があれば十分です。これを4つの脚すべてで行います。
ストッパー付きのキャスターがセットになっている場合(純正品は2個または4個)、デスクの前側(普段座る側)に取り付けると、足元でロック・解除の操作がしやすくなり便利ですよ。
ステップ5:デスクを起こして最終確認
最後に、倒したデスクを再び二人以上でゆっくりと元の状態に起こします。設置したい場所に移動させ、4輪全てのストッパーが正常に機能するか(ロック時に動かないか、解除時にスムーズに動くか)を確認すれば、すべての作業は完了です。お疲れ様でした!
W2とW3の違いは何ですか?
2024年5月以降、FlexiSpotの純正キャスターのラインナップが更新され、現在は「W2」と「W3」の2モデルが主力となっています。これらは旧モデル(W1)からデザインと性能が大幅に向上していますが、W2とW3の間にも明確な違いが存在します。どちらが自分の使い方に合っているか、詳しく比較検討しましょう。
両モデルの主な仕様の違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | キャスター W2 | キャスター W3 |
|---|---|---|
| デザイン | シンプルで機能的なブラック基調 | より大型で洗練されたメカニカルな印象 |
| 高さ(取付高) | 約68mm | 約73mm (W2より5mm高い) |
| 耐荷重(4個合計) | 公式情報で1000kg | 公式情報で3200kg |
| 価格(参考) | 3,300円前後 | 4,400円前後 |
| ロック機能 | 4個すべてにストッパー搭載 | 4個すべてにストッパー搭載 |
| 取り付け工具 | 付属しない (別途14mm薄型スパナが必要) | 付属しない (別途14mm薄型スパナが必要) |


どちらのモデルを選ぶべきか?
W2とW3の選択で最も重要な判断基準は、「デザインの好み」「価格」「わずかな高さの違い」の3点です。耐荷重については、W2の1000kgという数値ですら、FlexiSpotのどのデスクフレーム(最大でも200kg)に対しても十二分すぎるほどのオーバースペックです。W3の3200kgという耐荷重は、一般的なデスク用途では性能を持て余すことになります。
したがって、特別なこだわりがない限り、価格が1,000円以上安く、高さもわずかに抑えられるW2モデルが、最もコストパフォーマンスに優れた合理的な選択と言えるでしょう。
一方で、W3のより重厚感のあるデザインが、E7 ProやE7Hといったハイエンドモデルのデスク脚と視覚的にマッチすると感じる方もいるかもしれません。デスク下の見た目にまでこだわりたい場合は、価格差を許容してW3を選ぶのも一つの選択です。
純正と社外品、どちらがおすすめ?
FlexiSpotデスク用キャスターの選択肢は、メーカー純正品だけではありません。ネジ規格がM8であるため、非常に多くの安価で高機能な社外品(サードパーティ製品)も利用可能です。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理し、どのような基準で選ぶべきかを解説します。
メーカー純正品のメリット・デメリット
- メリット:
- メーカーによる製品保証が付帯しており、万が一の際も安心。
- デスク本体との適合性が100%保証されている。
- デザインの親和性が高く、統一感のある仕上がりになる。
- デメリット:
- 社外品と比較して、価格が2倍から3倍程度高い。
- ホイールの素材などが限定され、選択の幅が狭い。
「何よりも安心感を最優先したい」「初期不良などのリスクを完全に避けたい」という方には、やはりメーカー純正品が最もおすすめです。
社外品のメリット・デメリット
- メリット:
- 価格が圧倒的に安い。1,500円~2,500円程度で十分な品質のものが手に入る。
- 床を傷つけにくいウレタン製ホイールなど、機能や素材の選択肢が豊富。
- デザインや色のバリエーションが多い。
- デメリット:
- 品質にばらつきがあるため、信頼できるメーカーや販売者を選ぶ必要がある。
- 取り付けや使用はすべて自己責任となり、メーカー保証の対象外。
- ほとんどの製品で14mmスパナが別途必要になる。
結論:どちらを選ぶべきか?
コストパフォーマンスを重視し、ある程度の自己判断で製品を選べる方であれば、信頼性の高いメーカーの社外品が断然おすすめです。特に、日本の工具・産業用部品メーカーであるTRUSCO(トラスコ中山)や、キャスター専門メーカーのユーエイキャスターなどが販売しているM8規格の製品は、品質が安定しており、多くのユーザーから高い評価を得ています。
一方で、数千円の価格差よりも、手間なく確実に適合し、保証が付いているという安心感を優先したい方は、純正品(特にコストと性能のバランスが良いW2モデル)を選ぶのが賢明な判断と言えるでしょう。
キャスターの耐荷重は?
キャスターの耐荷重は、重い電動昇降デスクを安全に支えるための最も重要な性能指標です。耐荷重が不足していると、キャスターの破損やデスクの転倒といった重大な事故につながる可能性があります。
まず、ご自身のデスク環境の総重量を把握することが大切です。総重量は以下の式で概算できます。
総重量 = デスクフレームの重量 + 天板の重量 + 搭載機材の総重量
FlexiSpotのデスクフレームは約30kg~、天板も10kg~20kg程度あります。これにPC本体、モニター(デュアルモニターなら2台分)、その他周辺機器の重量を加えると、多くの環境で総重量は60kg~100kg程度になります。
各キャスターの耐荷重比較(4個合計の静止耐荷重)
- 純正品 W1(旧型):100kg
- 純正品 W2:1000kg
- 純正品 W3:3200kg
- 代表的な社外品(TRUSCO製 φ40mm):160kg
- 代表的な社外品(TRUSCO製 φ50mm):240kg
- 代表的な社外品(TRUSCO製 φ60mm):324kg
耐荷重に関する最重要原則
デスク全体の耐荷重は、「デスクフレーム本体の耐荷重」と「取り付けたキャスター4個の合計耐荷重」を比べ、より低い方の数値が適用されるということを覚えておいてください。
例えば、フレーム耐荷重が125kgのE7モデルに、合計耐荷重100kgのキャスターを取り付けた場合、そのデスクに載せられる機材の上限は100kgまでとなります。逆に、フレーム耐荷重70kgのEF1モデルに、合計耐荷重240kgのキャスターを取り付けても、デスク全体の耐荷重は70kgのままです。
結論として、E7Qのような特殊な重量級4脚モデルを除けば、合計耐荷重が160kg以上ある社外品キャスターでも、安全マージンは十分に確保されていると言えます。ご自身のデスクの総重量を計算し、その1.5倍から2倍程度の耐荷重を持つキャスターを選ぶと、より安心して使用できるでしょう。
flexispotキャスターとスパナ使用時の注意点
- デスクの高さの変化
- 床に傷がつく可能性
- スタンディング時の揺れというデメリット
- 組み立て後のキャスター後付け方法
- まとめ:flexispotキャスターと取付用スパナの要点
デスクの高さの変化
FlexiSpotデスクにキャスターを取り付けることで得られる機動力は大きなメリットですが、その代償として避けられないのが「デスク全体の高さが上がってしまう」という物理的な変化です。
キャスター自体の高さ(地面からネジの根元までの「取付高」)の分だけ、デスクが昇降できる範囲全体が底上げされます。具体的にどのくらい高くなるかは取り付けるキャスターによりますが、一般的におおよそ5cmから7.5cmほど高くなります。
適切な作業姿勢が取れなくなるリスク
この高さの変化は、特に小柄な方や、椅子の座面高を低めに設定している方にとっては、作業環境の快適性を著しく損なう可能性があります。例えば、これまでピッタリだった椅子の高さでは足が床から浮いてしまったり、腕や肩に負担のかかる不自然な姿勢でキーボードを打つことになったりする恐れがあります。
キャスターを導入する前には、必ずメジャーなどを使ってシミュレーションを行いましょう。
「現在の最適な机の高さ」+「導入予定キャスターの取付高」=「キャスター導入後の机の高さ」
この計算後の高さでも、お使いの椅子で快適な姿勢が維持できるかを厳密に確認することが、導入後の失敗を防ぐ鍵となります。

高さを変えずに移動させたい場合の代替案
もしシミュレーションの結果、高さが合わないと判断した場合は、キャスターの導入は諦めるべきかもしれません。しかし、移動させたいという目的を叶える代替案があります。それは、家具の脚の下に敷いて滑りを良くするフェルト付きのシール「カグスベール」のような製品の活用です。これならば、デスクの高さをほとんど変えることなく、必要な時だけデスクをスライドさせて移動させることが可能になります。
床に傷がつく可能性
総重量が数十kgにもなる昇降デスクをキャスターで日常的に動かすとなると、床へのダメージは誰もが心配する点です。結論として、何の対策も講じなければ、フローリングやクッションフロアなどの床材に傷や凹みがつくリスクは極めて高いと言わざるを得ません。
キャスターのホイール素材と床材の相性
キャスターの性能を左右するホイール部分の素材は、主に「ナイロン」と「ウレタン」の2種類に大別されます。
- ナイロン製:
非常に硬く、耐荷重性や耐摩耗性に優れるため、産業用キャスターで多用されます。
しかし、その硬さゆえにフローリングや塩ビ製の床材との相性は悪く、細かな傷をつけやすいという大きなデメリットがあります。 - ウレタン製:
ナイロンに比べて柔らかく、ゴムのような弾性を持つ素材です。
床面への追従性が高く、衝撃を吸収するため、走行音が静かで床に傷をつけにくいのが最大の特徴です。
室内用の家具やオフィスチェアで推奨されます。

最善かつ必須の対策は「保護マット」の使用
床に優しいウレタン製キャスターを選んだとしても、根本的な問題は解決しません。それは、デスクの重い荷重が、わずか4つの小さな接点に集中し続けるという事実です。これにより、長期間デスクを同じ場所に設置していると、床材がその圧力に耐えきれずに凹んでしまう「設置痕」が残るリスクが非常に高いのです。
したがって、床を完璧に保護するための最も確実な方法は、デスクの脚が乗る範囲に専用の保護マットを敷くことです。透明で目立ちにくいポリカーボネート製のチェアマットや、より広範囲をカバーできる硬質のジョイントマットなどを下に敷くことで、荷重が分散され、傷や凹みから床を確実に守ることができます。
スタンディング時の揺れというデメリット
キャスターを取り付けることで生じるデメリットの中で、特に使用感に直結するのが「安定性の低下」、具体的には「スタンディング時の揺れ」です。これは、デスクの支持構造が変化することに起因します。
元々デスクに付属しているアジャスターは、比較的広い面積を持つ円盤状の「面」でデスクをどっしりと支えます。一方、キャスターは小さな車輪の接地面という「点」でデスクを支える構造になります。物理的に、支持面積が小さくなるため、外部からの力に対して揺れやすくなるのは避けられません。
もちろん、作業に集中できないほどグラグラと揺れるわけではありません。しかし、アジャスター設置時と比較すれば、特にデスクを高く上げて立って作業している際に、タイピングの振動や腕の動きでモニターがわずかに揺れるのを感じやすくなるのは事実です。この感覚には個人差が大きいですが、事前に認識しておくべき重要な点です。
揺れを少しでも軽減するための工夫
- ストッパーの完全なロック:
基本中の基本ですが、作業中は4輪すべてのストッパーを確実にロックすることが揺れを最小限に抑えます。 - 車輪径の大きなキャスターの選択:
一般的に、車輪の直径(φ)が大きなキャスターほど、走行安定性だけでなく設置時の安定性も向上する傾向にあります。
迷ったら、少しでも径の大きなモデルを選ぶのが良いでしょう。 - デスク上の重量バランスの最適化:
重いPC本体などを床置きにする、モニターアームを使って重心を中央に寄せるなど、デスク上の重量バランスを整えることも、揺れの軽減に繋がります。
特に揺れに対して敏感な方や、ペンタブを使った描画など精密な作業を行う方は、この安定性低下のデメリットを十分に考慮した上で、キャスター導入の是非を判断してください。
組み立て後のキャスター後付け方法
「すでにデスクを組み立てて快適に使っているけれど、やっぱり移動させたくなった」という状況は非常によくあります。しかし、一度完成して重量物となったデスクに後からキャスターを取り付けるのは、組み立て時以上に注意と工夫が求められる作業です。
原則として最も安全な方法:デスクを倒す
何度か繰り返しますが、最も安全で確実な方法は、手間を惜しまず、一度デスク上の機材を全て片付け、二人以上で慎重にデスクを横に倒して作業することです。これが、怪我や家財の破損といったリスクを限りなくゼロに近づける唯一の方法です。
一人作業の最後の切り札:「エアージャッキ」
どうしても人手が確保できず、一人で作業せざるを得ない場合に限り、「エアージャッキ(リフトバッグ)」という道具が役立ちます。これは、車のタイヤ交換などに使われるジャッキの家庭版で、薄い袋をデスクの脚と床の隙間に差し込み、手動ポンプで空気を入れることで、テコの原理で数十kgの重量物を数cm持ち上げることができる便利な工具です。
エアージャッキ使用時の絶対的な安全ルール
エアージャッキは非常に便利ですが、使い方を誤ると重大な事故につながります。使用する際は以下の点を必ず守ってください。
- 耐荷重の確認:
製品の耐荷重がお手持ちのデスクの重量を上回っていることを確認してください。 - 物理的な支えを併用する:
ジャッキでデスクを持ち上げたら、作業する脚の近くに、必ず辞書や分厚い雑誌、角材などを挟み込み、万が一ジャッキから空気が抜けてもデスクが落下しないための「保険」をかけてください。 - ゆっくりと作業する:
空気を入れるのも抜くのも、急がずゆっくりと行い、常にデスクが不安定になっていないかを確認しながら作業を進めましょう。
安全を最優先事項として、細心の注意を払って作業に臨んでください。
まとめ:flexispotキャスターと取付用スパナの要点
この記事で解説した、FlexiSpotデスクのキャスター導入と、その際に必須となるスパナに関する重要なポイントをまとめます。
- FlexiSpotの現行純正キャスター(W2, W3)には取り付け工具が付属しない
- 必要なスパナは「幅14mm」かつ「厚さ3mm以下」の薄型板スパナ
- スパナはホームセンターやAmazonなどで数百円程度で入手可能
- FlexiSpotデスクのキャスター用ネジ穴の規格は「M8」サイズ
- M8規格であれば安価で高機能な多くの社外品キャスターも使用できる
- 取り付け作業は、安全のためデスクを倒して二人以上で行うのが原則
- 純正キャスターW2とW3の主な違いはデザイン、耐荷重、価格
- 耐荷重はオーバースペックなため、価格の安いW2が合理的選択肢
- コストを最優先するならTRUSCOなど信頼できるメーカーの社外品がおすすめ
- キャスターの合計耐荷重は、デスクと機材の総重量に十分な余裕を持たせる
- キャスター装着によりデスク全体の高さが約5cm~7.5cm上昇する
- 特に小柄な方は、高さの変化が作業姿勢に影響ないか事前確認が必須
- フローリングなど床への傷や凹みを防ぐため、保護マットの使用を強く推奨
- ホイール素材は床に優しい「ウレタン製」が室内利用には適している
- アジャスター設置時に比べ、スタンディング作業時の揺れは若干増加する
- 組み立て後の後付けには「エアージャッキ」が便利だが、安全対策は必須
- 高さを変えずに移動したい場合は「カグスベール」等が代替案になる