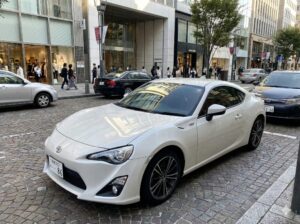DIYや家庭でのごみ処分で、プラスチック製品を切りたい場面は意外と多いものです。
そのとき、「家にある木工用ノコギリでプラスチックを切っても大丈夫?」と疑問に思ったことはありませんか。
実は、のこぎりの刃の使い分けは非常に重要で、何も知らずに使うと失敗や後悔につながる可能性があります。
この記事では、まず「そもそも木工用ノコギリは何に使いますか?」や「剪定用ノコギリと木工用ノコギリの違いは何ですか?」といった基本的な疑問から、プラスチック用のこぎりの違いについて掘り下げていきます。
さらに、金属用ノコギリの違いや、のこぎりの素材は何ですか、海外のノコギリと日本のノコギリの違いは何ですか、といった少し専門的な内容にも触れます。
のこぎりの種類 一覧として生木を切るタイプも紹介し、幅広い知識を提供します。
また、ホームセンターで見かけるなんでも切れるノコギリの性能や、ダイソーなど100均で手に入るプラスチック用ノコギリの実用性、そして最終的にあなたの用途に合ったプラスチック用ノコギリ おすすめ品を見つけるためのヒントを解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 木工用や金属用など、のこぎりの種類ごとの違い
- プラスチックを切るのに適したのこぎりの選び方
- 100均やホームセンターで買える製品の特徴
- 素材に応じた正しいのこぎりの使い分け

本記事の内容
プラスチック用のこぎりの違いを理解するための基礎知識
- そもそも木工用ノコギリは何に使いますか?
- 剪定用と木工用ノコギリの違いは何ですか?
- 金属用ノコギリとの違いとプラスチックへの応用
- のこぎりの種類一覧 生木用も解説
- 海外のノコギリと日本のノコギリの違いは何ですか?
- のこぎりの素材は何ですか?
そもそも木工用ノコギリは何に使いますか?
木工用ノコギリは、その名の通り、木材を加工するために特化した道具です。
主な用途は、木材を切断して目的の長さや形に整えることです。
DIYで家具を作ったり、棚を取り付けたりする際には欠かせません。

木工用ノコギリには、切断する木目の方向によって大きく分けて「横挽き(よこびき)」と「縦挽き(たてびき)」の2種類の刃があります。
横挽き刃は、木の繊維を断ち切るように、木目に対して直角に切断するために使われます。
一方、縦挽き刃は、木目に沿って繊維を削り取るように切断する際に使用します。
最近では、これらの刃が一本にまとまった「両刃ノコギリ」や、縦・横・斜めに対応できる「万能刃」を備えた片刃ノコギリが主流です。
したがって、木工用ノコギリは、木材を効率的かつきれいに切断するために、刃の形状が工夫されている道具と言えます。
剪定用と木工用ノコギリの違いは何ですか?
剪定用ノコギリと木工用ノコギリは、どちらも木を切る道具ですが、対象とする「木」の状態が根本的に異なります。
この違いが、それぞれの刃の形状や機能に大きく影響しています。

剪定用ノコギリは、庭木や果樹などの「生木」を切るために設計されています。
生木は水分を多く含んでいるため、おが屑が湿って刃に詰まりやすいです。
そのため、剪定用ノコギリの刃は、木工用に比べて刃と刃の間隔(ピッチ)が広く、おが屑を排出しやすい「アサリ」(刃が左右に交互に開いている加工)が大きめに作られています。
また、刃にはサビ防止のコーティングが施されていることが多いのも特徴です。
一方で、木工用ノコギリは、乾燥した木材を精密に加工することを目的としています。
そのため、切り口がきれいになるように刃のピッチが細かく、剪定用に比べてアサリが小さいか、全くない製品もあります。
生木を木工用ノコギリで切ろうとすると、目詰まりを起こして非常に効率が悪くなります。
逆に、剪定用ノコギリで乾燥木材を切ると、切断面が荒くなり、精密な作業には向きません。
このように、対象とする木材の水分量の違いが、二つのノコギリの最も大きな違いとなります。
金属用ノコギリとの違いとプラスチックへの応用
金属用ノコギリは、木工用やプラスチック専用ノコギリとは、刃の材質と形状に明確な違いがあります。
この違いを理解することで、プラスチック切断への応用が見えてきます。

金属用ノコギリの刃は、非常に硬い金属を切断するために、刃先には「ハイス鋼(高速度工具鋼)」などの硬い素材が使われています。
刃の形状は、木工用のように繊維を切るためのナイフ状ではなく、非常に細かいギザギザが並んでいるのが特徴です。
この細かい刃は、硬い素材を少しずつ削り取っていくのに適しています。
一方、プラスチックは木材のような繊維がないため、実は木工用の刃よりも金属用の細かい刃の方がスムーズに切断できる場合があります。
実際に、多くの金属用ノコギリはプラスチックの切断にも対応していると明記されています。
ただし、プラスチック専用のノコギリは、金属用と刃の形状は似ていますが、刃の硬さが異なります。
金属用でプラスチックを切るのは問題ありませんが、プラスチック専用ノコギリで金属を切ろうとすると、刃がすぐに摩耗してしまうため避けるべきです。
| のこぎりの種類 | 主な対象素材 | 刃の特徴 | プラスチック切断への適性 |
|---|---|---|---|
| 木工用ノコギリ | 乾燥木材 | 比較的大きな刃、 アサリが大きい、 繊維を切る形状 | △ (切れ味が悪く、切り口が荒れやすい) |
| 金属用ノコギリ | 鉄、アルミ、 銅など | 非常に細かい刃、 硬い材質(ハイス鋼など) | 〇 (問題なく切断可能) |
| プラスチック用 ノコギリ | 塩ビ、 アクリルなど | 細かい刃、 金属用よりは軟らかい材質 | ◎ (最適、切り口が綺麗に仕上がる) |
これらのことから、もし手元に金属用ノコギリがあれば、プラスチックの切断に代用することは可能です。
しかし、よりきれいな仕上がりを求めるなら、プラスチック専用品を使うのが最善の選択となります。
のこぎりの種類一覧 生木用も解説
のこぎりには、木工用やプラスチック用以外にも、さまざまな素材や用途に特化した種類が存在します。
ここでは、代表的なのこぎりの種類と、それぞれの特徴を一覧で紹介します。
生木用の剪定ノコギリもこの中に含まれます。
| 種類 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 両刃ノコギリ | 木工(縦挽き・横挽き) | 一本で木目の異なる方向に対応できる 伝統的なのこぎり。 |
| 胴付きノコギリ | 精密な木工、細工 | 刃が薄く、背中に補強がある。 切り口が非常にきれいに仕上がる。 |
| 廻し引きノコギリ | 曲線切り、くり抜き加工 | 刃が細長く、板材に穴を開けてから差し込んで 曲線を描くように切れる。 |
| ダボ切りノコギリ | ダボの切断、 表面の突起除去 | アサリがなく、刃がしなる。 材料の表面を傷つけずに突起物を切断できる。 |
| 剪定ノコギリ (生木用) | 庭木の剪定、伐採 | 水分を多く含む生木用。 目が粗く、おが屑が詰まりにくい。 |
| 竹挽きノコギリ | 竹の切断 | 竹の硬い繊維をきれいに切るため、 非常に細かい刃を持つ。 |
| 金切りノコギリ | 金属パイプ、 金属板の切断 | 刃の目が非常に細かく硬い。 プラスチックの切断にも使える。 |
| 万能ノコギリ | 粗大ゴミの解体など | 木材、プラスチック、 金属など複数の素材に対応できる刃を持つ。 |
このように、一口にのこぎりと言っても、その種類は多岐にわたります。

DIYや作業の内容に合わせて適切な一本を選ぶことが、効率と仕上がりの質を向上させる鍵となります。
特に、専門的な作業を行う場合は、その用途に特化したのこぎりを用意することが推奨されます。
海外のノコギリと日本のノコギリの違いは何ですか?
海外のノコギリと日本のノコギリには、工具としての哲学が反映された根本的な違いがあります。
最も大きな違いは、「引く」か「押す」かという力の加え方です。
日本のノコギリは、基本的に「引く」ときに材料を切断します。
刃を手前に引く動作で力を加えるため、刃自体を薄く作ることができます。
刃が薄いと、切り口の幅(切り幅)が狭くなり、材料の無駄が少なく、非常に精密で美しい切断面を得意とします。
また、引く力はコントロールしやすく、繊細な作業に向いています。

一方、西洋(海外)のノコギリは、「押す」ときに材料を切断するように設計されています。
押す力で刃が曲がってしまわないように、刃にはある程度の厚みと剛性が必要です。
そのため、日本のノコギリに比べて刃が厚く、切り幅も広くなります。
パワフルに、比較的スピーディーに材料を切断することに長けていますが、日本のノコギリほどの精密な切り口は得にくい傾向があります。
| 項目 | 日本のノコギリ | 海外のノコギリ |
|---|---|---|
| 力の方向 | 引くときに切断 | 押すときに切断 |
| 刃の厚さ | 薄い | 厚い |
| 切り幅 | 狭い | 広い |
| 得意な作業 | 精密な加工、きれいな切断面 | パワフルでスピーディーな切断 |
| 主な用途 | 建築、家具製作、細工 | 大工作業、フレーミング |
どちらが優れているというわけではなく、それぞれの文化や建築様式の中で発展してきた結果です。
日本の伝統的な木工技術では、精密な加工が求められるため「引きノコ」が主流となり、海外では頑丈な構造を素早く組み上げるために「押しノコ」が発展したと考えられます。
のこぎりの素材は何ですか?
のこぎりの性能を左右するのは刃の形状だけでなく、使われている素材も重要な要素です。
のこぎりは主に「刃」と「柄(え)」の二つの部分から構成されており、それぞれに適した素材が使用されています。
のこぎりの刃の素材
のこぎりの刃の多くは、「炭素工具鋼(SK材)」で作られています。
これは炭素を多く含んだ硬い鋼で、切れ味と耐久性のバランスが良いのが特徴です。
製品によっては、切れ味を長持ちさせるために「衝撃焼入れ」という熱処理が刃先に施されています。
また、サビを防ぎ、ヤニの付着を抑えるために「無電解ニッケルメッキ」などの表面処理がされているものも一般的です。
さらに硬い素材を切るための金切りノコや一部の高性能なノコギリには、刃先に「ハイス鋼(高速度工具鋼)」や、さらに硬い「超硬合金」が使われることもあります。
のこぎりの柄の素材
柄の素材は、握りやすさや耐久性に影響します。
伝統的なのこぎりでは、木製の柄に籐(とう)を巻いたものが多く見られます。
これは手に馴染みやすく、滑りにくいという利点があります。
現代では、より安価で成形しやすいプラスチック製の柄が主流です。
特に、握る部分に「エラストマー樹脂」というゴムのような柔らかい素材を使用したガングリップタイプは、滑りにくく力を入れやすいため、多くの製品で採用されています。
折りたたみ式ののこぎりでは、軽量で丈夫なアルミダイカスト製の柄が使われることもあります。
このように、のこぎりは刃から柄まで、用途に応じた素材が巧みに使い分けられています。
プラスチック用のこぎりの違い:選び方と使い方
- 木工用ノコギリでプラスチックを切る際の注意点
- 素材に合わせたのこぎりの使い分けのコツ
- ホームセンターで探すなんでも切れるノコギリ
- ダイソーなど100均のプラスチック用ノコギリは?
- 目的別!プラスチック用ノコギリのおすすめは?
- 【まとめ】プラスチック用のこぎりの違いを知り賢く選ぶ
木工用ノコギリでプラスチックを切る際の注意点
手元にある木工用ノコギリでプラスチックを切ろうと考える方もいるかもしれませんが、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
結論から言うと、切ること自体は可能ですが、推奨はされません。

第一に、作業効率が著しく低下します。
前述の通り、木工用の刃は木の繊維を切るために設計されています。
繊維のない均質なプラスチックに対しては刃がうまく食い込まず、滑るような感覚でなかなか切り進めることができません。
無理に力を加えると、刃が欠けたり曲がったりする原因にもなります。
第二に、切り口が汚くなる可能性が高いです。
木工用の大きな刃は、プラスチックの表面をきれいに切断するのではなく、むしり取るように削っていきます。
そのため、切り口にはバリが多く発生し、ギザギザで見栄えの悪い仕上がりになってしまいます。
アクリル板のような硬質プラスチックの場合、最悪のケースでは割れやヒビが入ることも考えられます。
第三に、摩擦熱でプラスチックが溶けることがあります。
特に塩ビなどの熱に弱いプラスチックを木工用ノコギリで速く切ろうとすると、摩擦熱で溶けたプラスチックが刃に付着し、切れ味をさらに悪化させる悪循環に陥ります。
これらの理由から、一時的な応急処置ならまだしも、本格的な作業やきれいな仕上がりを求める場合には、木工用ノコギリでプラスチックを切るのは避けるべきです。
素材に合わせたのこぎりの使い分けのコツ
のこぎりの性能を最大限に引き出すには、切断する素材に合わせて刃を正しく使い分けることが鍵となります。
刃の使い分けを判断するための主なポイントは、「刃のピッチ(細かさ)」、「アサリの有無」、「刃の厚さ」の3つです。

まず、「刃のピッチ」は仕上がりと作業スピードに直結します。
木材の精密加工や、アクリル板のような硬くてきれいな切り口が求められる素材には、ピッチが細かい(刃の数が多い)ものを選びます。
逆に、生木の剪定や角材の荒切りなど、スピードを重視する場合は、ピッチが粗い(刃の数が少ない)ものの方が効率的です。
次に、「アサリの有無」です。
アサリは、おが屑を排出しやすくし、摩擦を減らす役割がありますが、切り口の幅が広がり、表面がやや荒れる原因にもなります。
そのため、一般的な木材や生木の切断にはアサリ有りのものが適していますが、化粧板の切断やダボ切りなど、材料の表面を傷つけたくない精密な作業では、アサリの無いノコギリが必須です。
プラスチック用の多くも、バリを抑えるためにアサリが無いか、非常に小さい設計になっています。
最後に「刃の厚さ」も考慮します。
刃が厚いほど剛性が高く、力を入れてもブレにくいため、太い材料の切断に向いています。
一方で、刃が薄いものは切り口の幅が狭く、材料のロスが少ないため、細かな細工に適しています。
最近は、刃だけを交換できる「替え刃式」ののこぎりが主流です。
一つの柄(グリップ)で、木工用、プラスチック用、金属用など、さまざまな種類の刃を付け替えることができます。
作業内容に応じて複数の替え刃を用意しておけば、一本ののこぎりで幅広い用途に対応できるため、DIYユーザーには特におすすめです。
ホームセンターで探すなんでも切れるノコギリ
ホームセンターの工具売り場に行くと、「万能ノコギリ」や「多目的廃棄物ノコギリ」といった、一本で様々な素材が切れることを謳った製品が目に入ります。
これらは、木材からプラスチック、カーペット、さらには鉄やステンレスまで対応できるとされており、非常に魅力的に映ります。
これらの「なんでも切れるノコギリ」は、特定の素材に特化しているわけではなく、多くの素材を「それなりに」切断できるように、刃のピッチや形状が中間的に設計されています。

最大のメリットは、その汎用性の高さです。
家庭で出る様々な粗大ゴミを解体して小さくしたい場合や、DIYで多種多様な素材を少しずつ使う場合など、何本も専用のノコギリを揃える必要がないため、経済的で収納場所にも困りません。
一方で、デメリットも存在します。
それは、「器用貧乏」になりがちであるという点です。
例えば、木材を切るスピードや切り口の綺麗さは木工用ノコギリに劣りますし、プラスチックを切ったときの仕上がりも専用品には及びません。
金属の切断も可能ですが、金切りノコに比べると時間と労力がかかります。
したがって、なんでも切れるノコギリは、プロの職人のような高い精度や効率を求めない一般的な家庭での使用、特に「解体」を主な目的とする場合に非常に便利な道具です。
しかし、美しい作品を作りたいDIYや、特定の素材を頻繁に切る作業では、やはりそれぞれの専用ノコギリを用意する方が、結果的に満足度の高い作業ができるでしょう。
ダイソーなど100均のプラスチック用ノコギリは?
近年、ダイソーをはじめとする100円ショップでも、DIY用品が充実しており、プラスチックを切断できると謳うノコギリを見かけることがあります。
これらの製品は、その圧倒的な低価格が最大の魅力です。
数百円で手に入るため、「たまにしか使わない」「一度きりの作業で十分」といったニーズにはぴったりです。
例えば、収納ケースのちょっとした加工や、小さなプラスチック製品の解体など、軽作業であれば十分に役割を果たしてくれる場合があります。
しかし、価格が安い分、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。
まず、耐久性や刃の持続性は、ホームセンターなどで販売されている専門メーカーの製品には及びません。
刃の材質や熱処理が異なるため、硬いプラスチックを切ったり、長時間使用したりすると、切れ味がすぐに落ちてしまうことが多いです。
また、多くの100均ノコギリは刃の交換ができない使い切りタイプです。
切れ味が悪くなったら本体ごと買い替える必要があり、長期的に見ると必ずしも経済的とは言えないかもしれません。
グリップの形状も簡素なものが多く、力を入れにくかったり、長時間の作業で手が疲れやすかったりすることもあります。
結論として、100均のプラスチック用ノコギリは、「ごく稀に行う、短時間の軽作業」にはコストパフォーマンスの高い選択肢となり得ます。
しかし、定期的なDIYや、ある程度の強度や精度が求められる作業には、やはり信頼できる工具メーカー製の、切れ味が長持ちし、刃の交換も可能なノコギリを選ぶことを強くおすすめします。
目的別!プラスチック用ノコギリのおすすめは?
プラスチックと一口に言っても、その種類や形状は様々です。
それぞれの目的に合わせて最適なノコギリを選ぶことで、作業は格段に快適で、仕上がりも美しくなります。
ここでは、代表的な目的別に、どのようなタイプのプラスチック用ノコギリがおすすめかを解説します。
塩ビパイプの切断には「パイプソー」
水道管や排水管のDIYで塩ビパイプを切断する機会は多いです。
この用途には、「パイプソー」や「エンビソー」と呼ばれる専用のノコギリが最適です。
これらのノコギリは、パイプのような曲面にも刃がしっかりと食い込み、ブレずにまっすぐ切れるように設計されています。
刃のピッチも塩ビの切断に適した細かさになっており、スムーズな切れ味とバリの少ないきれいな切り口が特徴です。
アクリル板や硬質プラスチックの精密加工には「細工用ノコギリ」
アクリル板やデコラ板など、硬くて割れやすいプラスチックをきれいに切断したい場合は、刃が非常に細かい「細工用ノコギリ」や「樹脂用」と明記された精密ノコギリがおすすめです。
特に、刃が薄く、背中に補強が入った「胴付きタイプ」のものは、直進性に優れ、非常に美しい切断面を得られます。
切り口をヤスリで仕上げる手間を大幅に減らすことができます。
小物の製作や曲線切りには「クラフトのこ」や「引廻しノコ」
模型製作や小物のDIYでプラスチックを加工するなら、小回りの利く「クラフトのこ」が便利です。
カッターナイフのような形状で扱いやすく、細かい作業に適しています。
また、板状のプラスチックに穴を開けたり、曲線で切り抜いたりしたい場合は、刃が細長い「引廻しノコ」が活躍します。
ドリルで下穴を開ければ、板の中央からでも切り始めることが可能です。
このように、プラスチックを切るという一つの作業でも、対象物の材質や形状、そして求める仕上がりのレベルによって、選ぶべきノコギリは変わってきます。
自分の作業内容を明確にして、最適な一本を見つけることが大切です。
【まとめ】プラスチック用のこぎりの違いを知り賢く選ぶ
この記事では、のこぎりのプラスチック用と他の種類との違いについて、多角的に解説してきました。
最適な一本を選ぶためには、これらの違いを理解し、自身の用途に合わせて賢く選択することが大切です。
最後に、重要なポイントをまとめます。
- 木工用ノコギリは木の繊維を切るための刃を持つ
- プラスチックには繊維がないため木工用は不向き
- 木工用でプラスチックを切ると効率が悪く切り口も荒れる
- 剪定用は水分を多く含む生木を切るためのノコギリ
- 剪定用は刃の目が粗く、乾燥木材やプラスチックには向かない
- 金属用は刃が非常に細かく硬い材質でできている
- 金属用の刃はプラスチックの切断にも応用できる
- プラスチック専用品は、金属用と刃の形は似ているが硬さが違う
- のこぎりの刃は「引く」日本のものと「押す」海外のもので根本的に異なる
- 刃の使い分けは「ピッチ(細かさ)」と「アサリの有無」が鍵
- 硬い素材やきれいな仕上がりには細かいピッチの刃が適している
- おが屑の排出やスピード重視なら粗いピッチの刃を選ぶ
- ホームセンターの万能ノコギリは解体作業には便利だが専門性には劣る
- 100均のノコギリは軽作業には使えるが耐久性は低い
- 塩ビパイプにはパイプソー、アクリル板には細工用など目的に応じた専用品を選ぶのが最善
- 替え刃式のノコギリなら一本の柄で様々な素材に対応可能